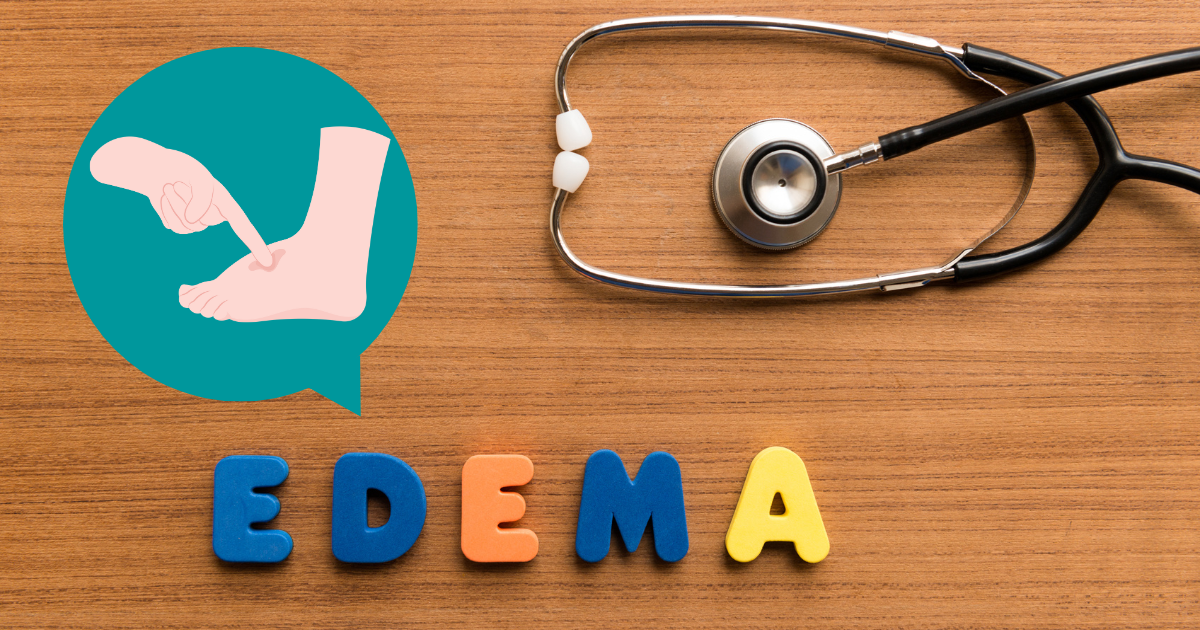浮腫について|観察項目から看護のポイントまで徹底解説
 あずかん
あずかん「浮腫」は、病棟や外来で最も頻繁に遭遇する身体所見の一つです。そのため、「足がむくんでますね、挙上しておきましょう」で終わらせていませんか?
実はその浮腫、心不全の増悪かもしれませんし、低栄養の進行、あるいは見逃してはいけないDVT(深部静脈血栓症)のサインかもしれません。
浮腫を単なる「水分貯留」として片付けるのではなく、「血管内と血管外で何が起きているか(スタルリングの法則)」をイメージしながらアセスメントすることで、患者さんの急変リスクや隠れた病態を浮き彫りにすることができます。
今回は、現場ですぐに使える臨床推論に基づいた「浮腫アセスメント」を解説します。
目次
【保存版】原因を突き止めるための観察項目&根拠
| 観察項目 | 観察ポイント | 根拠・予測 |
|---|---|---|
| 圧痕の性状(Pitting / Non-pitting)と回復時間 | 脛骨前面や足背を親指で10秒以上強く圧迫し、指を離した後の「凹み」を確認する。 ・Fast edema:すぐ戻る(40秒以内) ・Slow edema:なかなか戻らない(40秒以上) | ①低アルブミン血症(膠質浸透圧低下)による浮腫は、組織液の粘度が低いためFast edemaになりやすい傾向があります。 ②一方、心不全(静水圧上昇)による浮腫は、組織間液の移動に時間がかかるためSlow edemaになりやすいです。 ※甲状腺機能低下症やリンパ浮腫は、ムコ多糖類の貯留によりNon-pitting(圧痕を残さない)となるのが特徴的です。 |
| 浮腫の分布(全身性 vs 局所性) | 両下肢だけでなく、顔面(眼瞼)、背部(仙骨部)、上肢も確認する。 寝たきりの患者さんは仙骨部や陰嚢に水分が移動するため、下肢だけ見て「浮腫なし」と判断しない。 | 全身性浮腫(両側性)は、心不全、腎不全、肝硬変、低栄養など、全身の循環・代謝異常を示唆します。 一方、局所性浮腫(片側性)は、DVT、蜂窩織炎、リンパ流閉塞など、その部位特有のトラブル(閉塞・炎症)を強く疑います。 「片足だけ腫れている」は緊急性が高い(DVTリスク)と覚えておきましょう。 |
| 頸静脈怒張(JVD)の有無 | ベッドを45度にギャッジアップし、患者さんに顔を横に向けてもらい、胸鎖乳突筋の後ろにある外頸静脈が怒張していないか確認する。 呼吸に伴う変動も見る。 | 右心不全の指標です。浮腫があり、かつ頸静脈怒張があれば、原因は「体液過剰(溢水)」である可能性が極めて高いです。 逆に、浮腫があっても頸静脈が虚脱していれば、血管内脱水を伴う低アルブミン血症(血管外への漏出)などを疑い、利尿剤の使用には慎重になる必要があります。 |
| 体重変動とIN/OUTバランス | 毎朝の体重測定(できれば排尿後、同じ衣類で)を行う。 「1週間で2kg増加」のような急激な変化がないか、前日比だけでなく週間推移を見る。 | 浮腫として目に見えるようになるには、体重の約10%(数kg)の水分貯留が必要と言われています。 つまり、浮腫が出現した時点で相当量の水分が溜まっています。短期間での急激な体重増加は、ほぼ間違いなく水分の貯留(心不全増悪など)を意味します。 |
| 皮膚の熱感・発赤・疼痛 | 手背を使って左右の皮膚温を比較する。 また、浮腫部位を把持した際に患者さんが痛がるか(圧痛・把握痛)を確認する。 | 通常の心性・腎性浮腫は冷たく、痛みも伴いません。 もし熱感や発赤、疼痛があれば、蜂窩織炎やDVT(血栓性静脈炎)などの炎症性機序を疑います。DVTの場合、不用意なマッサージは肺塞栓(PTE)を誘発する禁忌行為となるため、鑑別は必須です。 |
現場で役立つ+αの看護ポイント
「利尿剤が効いているか」は尿量だけでは不十分
利尿剤(ラシックス等)開始後、尿量が増えるのは当然ですが、「血圧が下がってきていないか」「脈拍が速くなっていないか(頻脈)」を必ずセットで見てください。
浮腫が残っていても、急激な利尿で血管内脱水が進んでいることがあります。この状態で利尿を続けると、腎機能悪化(Prerenal AKI)や脳梗塞のリスクになります。「足はむくんでいるのに、血管の中はカラカラ」という状態を見逃さないでください。
スキンケアは「保湿」と「保護」が命
浮腫のある皮膚は、表皮が薄く引き伸ばされており、バリア機能が著しく低下しています。テープを剥がす程度の刺激で表皮剥離(スキンテア)を起こしたり、わずかな傷から浸出液(リンパ液)が漏れ出したりします(リンパ漏)。
清拭時はこすらず「押さえ拭き」をし、保湿剤をたっぷり塗布すること。これが感染予防(蜂窩織炎予防)の最大のケアになります。