廃用性症候群とは|原因・症状・看護のポイントを徹底解説
 あずかん
あずかん寝たきりや長期の安静によって、心身の機能が低下する「廃用性症候群」。高齢者だけでなく、あらゆる年代の患者さんに起こりうるこの症候群は、看護の現場で避けては通れない重要な症状です。
この記事では、廃用性症候群の病態生理から原因、症状、治療、そして最も大切な看護のポイントまで、分かりやすく解説します。
目次
廃用性症候群とは
廃用性症候群は、英語で「Disuse Syndrome」と呼ばれます。これは、長期間にわたる安静や活動量の低下によって、身体の様々な器官や組織に機能低下や萎縮が生じる状態を指します。
私たちの身体は、適度な負荷や刺激を受けることでその機能を維持しています。しかし、活動がなくなると、身体は「その機能は不要だ」と判断し、エネルギーを節約するために各器官を縮小・機能低下させていきます。これが廃用性症候群の基本的なメカニズムです。
特に、重力に抗して身体を支える筋肉や骨、循環器系への影響は顕著に現れます。
廃用性症候群の主な原因
廃用性症候群の直接的な原因は「不動」、つまり体を動かさないことです。具体的な状況としては、以下のようなものが挙げられます。
絶対安静の指示: 骨折、心疾患、脳卒中などの急性期治療
麻痺や意識障害: 脳血管疾患や脊髄損傷による後遺症
痛み: 関節リウマチや術後の疼痛による活動制限
ギプス固定: 骨折治療による局所的な不動
認知症やうつ病: 意欲の低下による活動性の減少
過度な安静: 「転んだら危ないから」といった過剰な安静志向
全身に及ぶ症状
廃用性症候群の症状は、特定の部位だけでなく、全身のあらゆる器官に現れます。
| 分類 | 具体的な症状 |
|---|---|
| 筋骨格系 | 筋萎縮・筋力低下 特に下肢の抗重力筋(大腿四頭筋など)で著しい。1週間の安静で10〜15%の筋力低下が起こるとも言われる。 関節拘縮 関節を動かさないことで、関節包や周囲の組織が硬くなり、可動域が制限される。 骨萎縮(骨粗鬆症) 骨への力学的負荷が減少することで、骨形成よりも骨吸収が優位になり、骨がもろくなる。 |
| 循環器系 | 起立性低血圧 安静臥床により循環血液量が減少し、自律神経の調節機能も低下するため、急に起き上がると血圧が下がり、めまいや失神を起こす。 心機能低下 心拍出量が減少し、全身持久力が低下する。 深部静脈血栓症(DVT) 足の筋肉のポンプ作用が働かないことで血流が滞り、血栓ができやすくなる。これが肺に飛ぶと、致死的な肺血栓塞栓症(エコノミークラス症候群)を引き起こす。 |
| 呼吸器系 | 換気障害・沈下性肺炎 横隔膜や呼吸筋の筋力低下、仰臥位による肺の圧迫で、肺活量が減少。また、痰の排出が困難になり、細菌が溜まることで肺炎(沈下性肺炎)のリスクが高まる。 |
| 消化器系 | 食欲不振・便秘 活動量低下に伴い、消化管の蠕動運動も低下し、食欲不振や便秘につながる。 |
| 精神・神経系 | 精神機能の低下 外部からの刺激が減少し、感覚遮断に近い状態になることで、うつ状態、せん妄、見当識障害、認知機能の低下などを引き起こす。 |
| 皮膚 | 褥瘡 長時間同じ体勢でいることで、骨の突出部に圧力がかかり続け、血流障害が起きて皮膚組織が壊死する。 |
| その他 | 尿路結石・尿路感染症 長期臥床により骨からカルシウムが溶け出し、尿中のカルシウム濃度が上昇するため結石ができやすくなる。また、排尿障害やカテーテル留置により感染のリスクも高まる。 |
治療・対症療法
廃用性症候群の最も効果的な治療は「予防」です。
発症してしまった場合、治療の基本は早期離床と積極的なリハビリテーションになります。
- 理学療法(PT)
- 関節可動域訓練、筋力増強訓練、座位・立位訓練、歩行訓練などを行い、基本的な身体機能の回復を目指します。
- 作業療法(OT)
- 食事や着替え、排泄といった日常生活動作(ADL)の訓練を通じて、応用的な動作の再獲得と社会復帰を支援します。
- 言語聴覚療法(ST)
- 嚥下機能の低下に対して、嚥下訓練や食事形態の調整を行います。
- 栄養管理
- 低栄養は筋力低下を助長するため、十分なカロリーと、筋肉の材料となるタンパク質を摂取できるよう栄養サポートを行います。
- 薬物療法
- 深部静脈血栓症の予防・治療のための抗凝固薬など、合併症に対する対症療法が行われます。
看護のポイント
アセスメントとリスク評価
- リスクの早期発見
- ADL自立度、意識レベル、栄養状態、既存疾患などから、廃用性症候群のリスクが高い患者を早期に特定します。
- 全身状態の観察
- 皮膚の状態(褥瘡の兆候)、呼吸状態、循環動態(浮腫、血圧変動)、排泄状況、精神状態などを継続的に観察し、わずかな変化も見逃さないようにします。
早期離床と活動促進の援助
- 「動かさない」から「どう動かすか」へ
- 医師の指示の範囲内で、可能な限り早期から離床を促します。漫然と安静にするのではなく、「安静度」を正しく理解し、その範囲内で最大限の活動を引き出すことが重要です。
- 環境整備
- ベッドからポータブルトイレへの移動、ベッドサイドでの食事摂取など、少しでも座位の時間を作れるよう環境を整えます。
- リハビリテーションとの連携
- 理学療法士や作業療法士と密に連携し、病棟での自主トレーニングメニューの実施をサポートしたり、日常生活動作の中にリハビリの要素を取り入れたりします。
関節拘縮・筋力低下の予防
- 良肢位(機能的肢位)の保持
- 麻痺などがある場合、拘縮が起きても日常生活への支障が最も少ない肢位を保ちます。クッションや枕を効果的に使用します。
- 他動的な関節可動域訓練
- 患者自身で動かせない関節は、看護師がゆっくりと動かし、可動域を維持します。
褥瘡・深部静脈血栓症(DVT)の予防
- 体位変換
- 定期的な体位変換は、褥瘡予防の基本です。
- 弾性ストッキングの着用
- 医師の指示に基づき、適切なサイズの弾性ストッキングを正しく着用させ、DVTを予防します。
- 足関節の運動
- 患者自身で、あるいは看護師が介助して足関節の底背屈運動を行い、下肢の血流を促進します。
精神的サポート
- コミュニケーション
- 声をかけ、社会的なつながりを保つことで、せん妄やうつ状態を予防します。
- 意欲の引き出し
- 患者の「できること」や「好きなこと」に着目し、それを生活の中に取り入れることで、リハビリへの意欲や自尊心を高める支援をします。
ポンコツ看護師の勉強ログ




口腔内の廃用性症候群について | ポンコツ看護師の勉強ログ
最近、患者さんの口臭や食事のむせが気になりませんか?それは口腔廃用症候群かもしれません。この記事では、新人看護師向けに口腔廃用症候群の原因、症状、看護のポイント…
ポンコツ看護師の勉強ログ




静脈血栓塞栓症について | ポンコツ看護師の勉強ログ
【看護師・看護学生向け】静脈血栓症(VTE)の病態生理から原因、症状、最新治療、看護のポイントまで徹底解説。Virchowの3主徴やDVT・PTEの観察項目、抗凝固療法の注意点…
ポンコツ看護師の勉強ログ

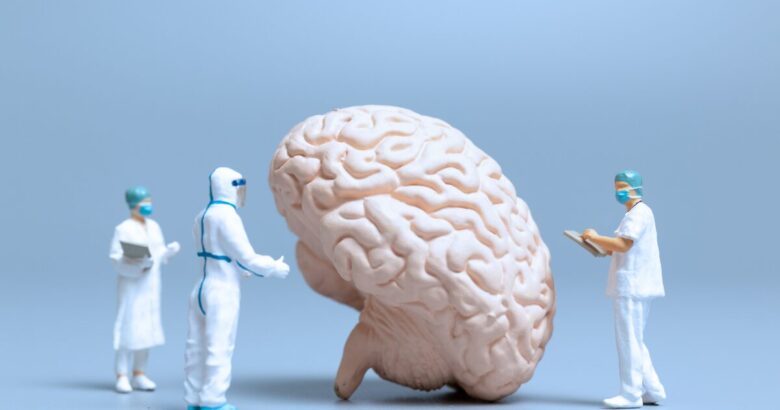
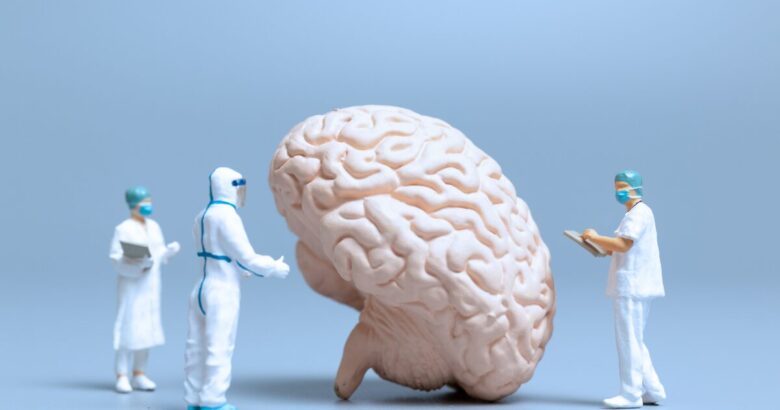
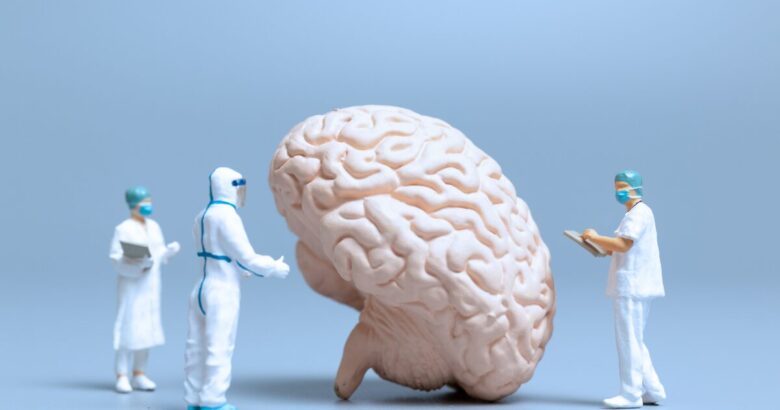
認知症について | ポンコツ看護師の勉強ログ
これから認知症患者さんを受け持つ看護学生・新人ナース必見!認知症の基礎知識(四大認知症の違いなど)から、現場で活かせるコミュニケーション術、BPSDの背景の読み解き…