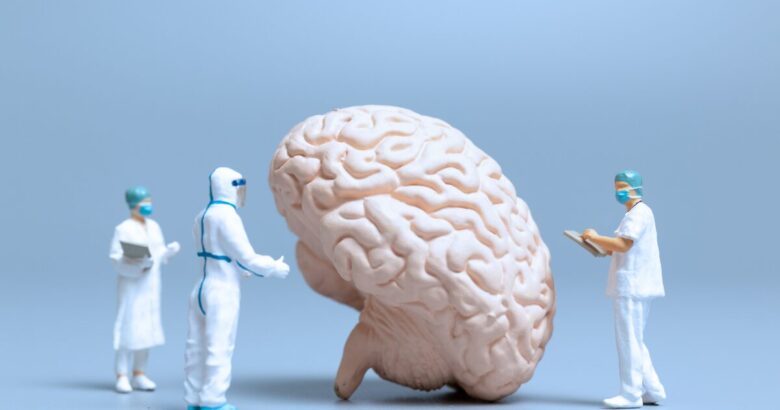水頭症について|疾患の概要から看護のポイントまで徹底解説
 あずかん
あずかん水頭症について、「シャント術後の管理」というイメージが強いかもしれませんが、実は術前の「なんとなく元気がない」「歩き方がおかしい」といった非特異的な症状から、私たち看護師が疾患の進行やシャント機能不全に気づけるかが鍵となる疾患です。
特に高齢者の特発性正常圧水頭症(iNPH)は、「トシのせい」で見過ごされがちですが、治療可能な認知症の代表格でもあります。
今回は、教科書的な知識に加え、明日からのアセスメントの引き出しの一つとして「観察の勘所」と「ケアの工夫」を紹介します。
サクッと復習!疾患の概要
- 病態: 脳脊髄液(CSF)の循環・吸収障害、または過剰産生により、脳室が拡大し、脳実質を圧迫する状態です。
- 分類
- 閉塞性水頭症(非交通性): 腫瘍などで髄液の通り道が塞がれるタイプ。急性進行しやすくICP(頭蓋内圧)亢進症状が出やすい。
- 交通性水頭症: 髄液の吸収障害が主。くも膜下出血(SAH)後や髄膜炎後によく見られます。
- 特発性正常圧水頭症(iNPH): 原因不明で、圧は正常範囲内だが脳室が拡大する高齢者に多いタイプ。
- 症状(ハキムの3徴候)
- 歩行障害(開脚歩行、小刻み歩行)
- 認知症(特に意欲低下・自発性低下といった前頭葉症状)
- 尿失禁(切迫性尿失禁)
- 治療
- 脳室-腹腔短絡術(V-Pシャント)、脳室-心房短絡術(V-Aシャント)、腰椎-腹腔短絡術(L-Pシャント)。
- 内視鏡下第三脳室底開窓術(ETV)。


観察ポイント&根拠
| 観察項目 | 看護のポイント | 根拠・予測 |
|---|---|---|
| 意識レベルと「自発性」の変化 | JCSやGCSのスコアリングだけでなく、「自分から話しかけてくる頻度が減っていないか」「食事の手が止まっていないか(ボーッとしていないか)」を確認する。 | 前頭葉への圧迫や脳血流低下により、意識障害の前段階としてアパシー(無気力・無関心)が出現します。「今日は大人しいな」ではなく、ICP亢進やシャント閉塞の初期サインである可能性を疑います。 |
| 歩行リズムと開脚度 | 歩行介助時、足のスタンス(左右の足の幅)が広がっていないか、すり足になっていないかを観察する。 | 側脳室の拡大により、内包を通る皮質脊髄路(特に下肢領域の神経線維)が伸展・圧迫されることで生じる特有の症状です。転倒リスク直結のサインであり、日々の変化が治療効果のバロメーターになります。 |
| シャントバルブ・走行上の皮膚所見 | 耳介後部などのバルブ埋没部を触診し、「ぷよぷよした液体貯留(皮下貯留)」がないか確認する。また、カテーテル走行に沿った発赤・熱感の有無を見る。 | バルブ周囲の液体貯留は、髄液の漏出や吸収不全を示唆します。また、カテーテル感染は髄膜炎に直結する重篤な合併症です。発熱前に局所の皮膚トラブルで気づけるかが勝負です。 |
| 頭痛・嘔気と体位の関係 | 「頭が痛い」という訴えがあった場合、「起き上がると痛いのか(低髄液圧症状)」、「寝ている時や朝方が痛いのか(ICP亢進症状)」を聞き分ける。 | シャントのオーバードレナージ(効きすぎ)では起立性頭痛が、アンダードレナージ(効きが悪い)ではICPが高まる早朝や臥位時に頭痛が増強します。圧設定の調整に必要な情報です。 |
もし患者さんが「トイレが間に合わなかった」と言ったら?
iNPHの患者さんなどでよくあるのが、尿意を感じてから排尿までの我慢がきかず、失禁してしまうケースです。
患者さんが「あぁ、また漏らしちゃった…情けない」と消沈している時、単に「大丈夫ですよ、着替えましょう」と事務的に処理するのは、プロの関わりとしては不十分です。
対応アクションと会話例
- 疾患の症状であることを明確に伝え、罪悪感を軽減する(教育的関わり)
- 「間に合わなくてショックでしたね。でも、これは〇〇さんの不注意のせいではなく、病気で脳の神経が圧迫されて、おしっこの指令がうまく伝わらないだけなんですよ。」
- 改善の可能性を示唆する(希望の提示)
- 「手術や治療で脳の圧迫が取れてくると、おしっこのコントロールも戻ってくる患者さんが多いんです。今は一時的な症状ですから、あまりご自分を責めないでくださいね。」
- 具体的な対策の提案(環境調整)
- 「今は我慢するのが難しい時期なので、こちらからも2時間おきに声をかけさせてもらいますね。ズボンも下ろしやすい緩めのものに変えてみましょうか。」
現場で差がつく看護のコツ・ポイント
水頭症のケアは、ドレナージ管理や術後の頭位管理など、少しの工夫で合併症リスクや患者さんの苦痛を減らせます。
| 工夫・コツ・アイデア | 具体的な手技・環境調整 | 期待される効果・メリット |
|---|---|---|
| シャントバルブ圧迫予防のポジショニング | 術後、バルブ(多くは耳の後ろ)がある側を下にして寝かせないよう、枕の位置を調整したり、ドーナツ枕を使用して耳介後部を浮かせる。 | 持続的な圧迫による皮膚壊死や褥瘡を防ぎます。特に高齢者の皮膚は菲薄化しているため、バルブ露出のリスク管理として非常に重要です。 |
| ギャッジアップ時の「めまい」対策 | シャント術後やドレナージ抜去後の離床時、急に頭を上げず、15度→30度→端坐位と、時間をかけて段階的に挙上し、その都度頭痛や気分の悪さを確認する。 | 急激な体位変換による髄液圧の変動(特にオーバードレナージによる低髄液圧)を防ぎ、硬膜下血腫や頭痛の誘発を回避します。 |
| 歩行介助時の「リズム出し」 | すり足歩行で足が出にくい患者さんに対し、「イチ、ニ、イチ、ニ」と声をかけたり、メトロノームを使ったりして聴覚刺激を入れる。 | 前頭葉機能低下による歩行開始困難に対し、外部からのリズム刺激が運動プログラムのスイッチとなり、スムーズな一歩が出やすくなります。 |
| 食事摂取時の「声かけ」継続 | 食事中に動きが止まってしまう(アパシー)患者さんに対し、叱咤するのではなく「お味噌汁、温かいうちにどうぞ」と具体的に次の動作を促す。 | 注意障害があるため、漠然と「食べて」と言うより、具体的な物品名を出すことで注意を喚起し、自立摂取を支援できます。 |
新人さんが陥りやすいミスへの対策
術後しばらく経過観察中の患者さんが「最近、日中もよく寝ているな」と思っていたのに、それを「入院生活に慣れて暇だから寝ているだけ」と解釈してしまいました。
実際は、シャント機能不全による軽度の意識レベル低下(傾眠傾向)でした。数日後に歩行状態が悪化して初めてCTを撮り、脳室が再拡大していることが発覚しました。
水頭症、特に慢性の経過をたどる場合、変化はとても緩やかです。
「麻痺がない」「話せばわかる」からといって油断しないでください。
「意欲の低下」「反応の鈍さ」「日中の過眠」は、ただの加齢現象や性格の変化ではなく、脳からのSOS(頭蓋内環境の悪化)かもしれません。
ご家族からの「家だともっとお喋りだったんですけどね」という言葉は、非常に感度の高い情報です。バイタルサインに現れない変化こそ、私たち看護師が拾い上げるべき重要なサインですよ。