蜂窩織炎の病態から看護のポイントまで徹底解説
 あずかん
あずかん蜂窩織炎は、皮膚科や救急外来でよくみられる細菌感染症の一つです。急性期には入院加療が必要になることもあり、看護師として正しい知識を持って対応することが求められます。
この記事では、蜂窩織炎の基本的な知識から、具体的な看護のポイントまでを分かりやすく解説します。
蜂窩織炎とは
蜂窩織炎は、皮膚の深い層である「真皮」から「皮下組織」にかけて、細菌が侵入し炎症を引き起こす疾患です。
私たちの皮膚は、外側から「表皮」「真皮」「皮下組織」という層構造になっています。通常、最も外側にある表皮がバリアとして機能し、細菌の侵入を防いでいます。しかし、何らかの原因でこのバリアが破られると、そこから細菌が真皮や皮下組織に侵入し、急激に増殖して炎症反応を引き起こします。
この炎症は、脂肪細胞を多く含む皮下組織の構造に沿って、水平方向に急速に拡大していく特徴があります。重症化すると、筋肉を覆う「筋膜」にまで炎症が及び、より重篤な「壊死性筋膜炎」に進行することもあるため、早期の診断と治療が非常に重要です。
蜂窩織炎の原因
蜂窩織炎の主な原因は、皮膚のバリア機能の破綻と、そこからの細菌感染です。
原因菌
黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus):最も一般的な原因菌の一つ。
レンサ球菌(Streptococcus属):特にA群β溶血性レンサ球菌が代表的。
これらの菌は、私たちの皮膚や鼻腔に普段から存在する常在菌ですが、皮膚の傷口などから体内に入り込むと、感染症を引き起こすことがあります。
感染経路
細菌が侵入するきっかけとなる皮膚の小さな傷には、以下のようなものがあります。
擦り傷、切り傷
虫刺され、動物による咬み傷
水虫(足白癬)による皮膚のびらんや亀裂
アトピー性皮膚炎などによる引っかき傷
ピアスの穴
手術創
リスクファクター
以下のような基礎疾患や状態は、蜂窩織炎を発症しやすく、また重症化させやすいリスクファクターとなります。
糖尿病:高血糖により免疫機能が低下し、血流障害も伴うため。
末梢血管疾患(ASOなど):血行不良により、感染防御能が低下する。
リンパ浮腫:リンパ液のうっ滞により、細菌が増殖しやすくなる。
免疫不全状態:ステロイドや免疫抑制薬の使用、HIV感染など。
肥満
高齢
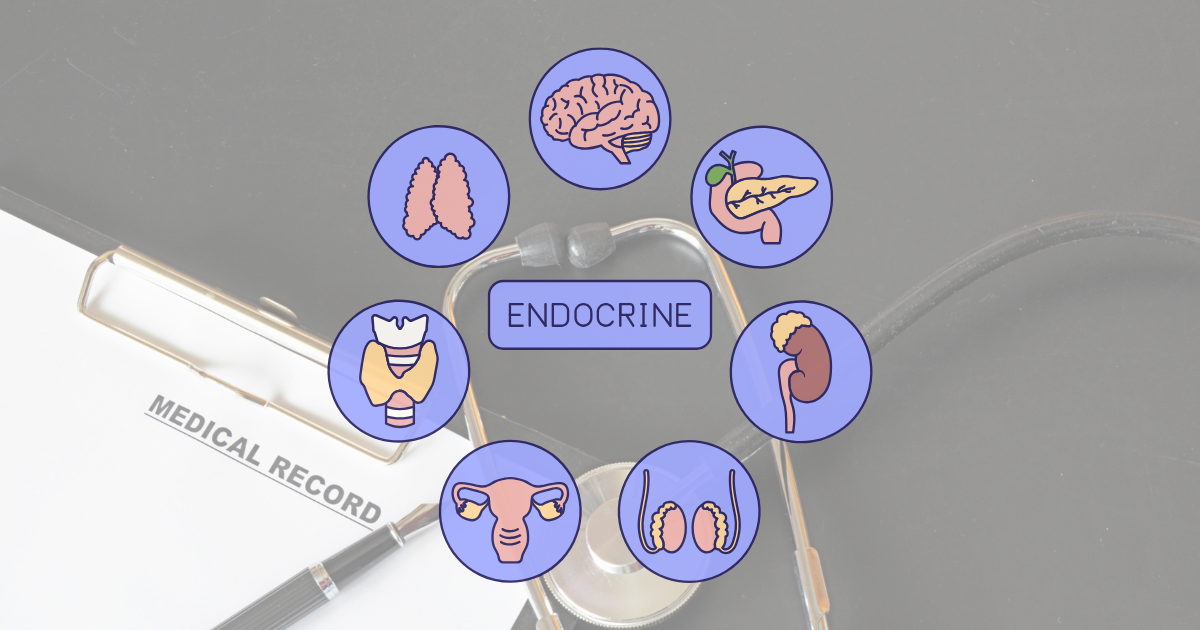
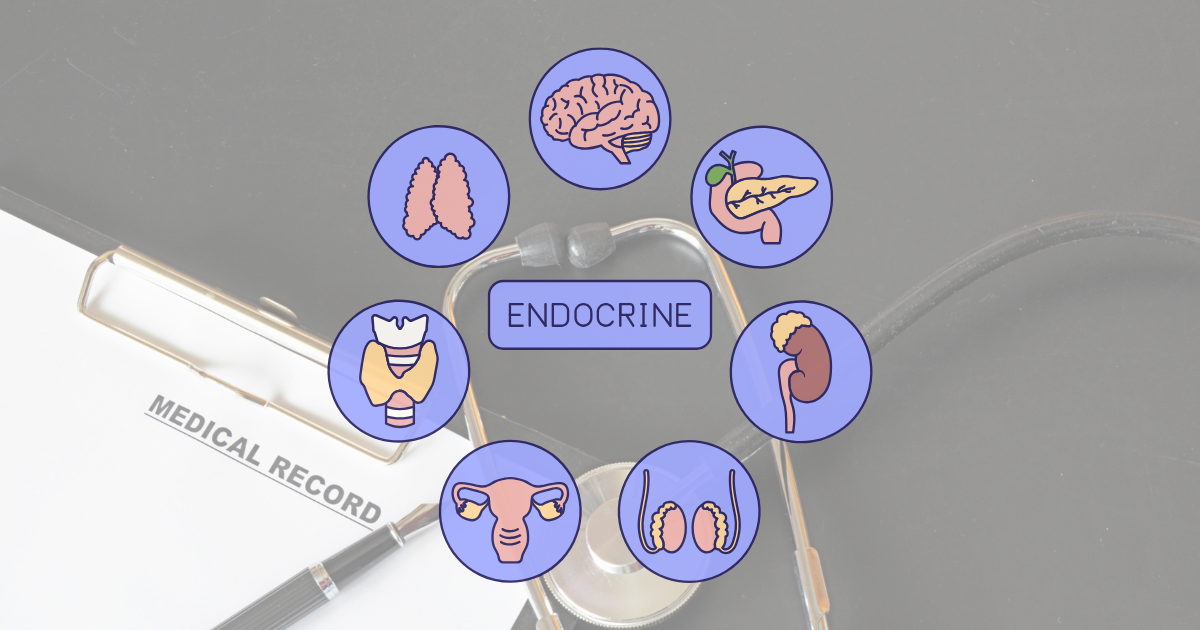
蜂窩織炎の症状
蜂窩織炎は、主に四肢、特に下肢に好発しますが、顔面や体幹にも起こり得ます。特徴的な局所の症状と、全身症状があります。
局所症状
炎症の4徴(+機能障害)が典型的にみられます。
- 発赤:境界がやや不明瞭な、びまん性の赤い腫れ。
- 熱感:患部が熱を持つ。
- 腫脹:むくんでパンパンに腫れあがる。
- 疼痛:自発痛や圧痛がある。特にレンサ球菌感染では痛みが強い傾向がある。
- 水疱形成:重症例では、水ぶくれができることがある。
- 所属リンパ節の腫脹・圧痛
全身症状
炎症が強くなると、全身に症状が広がります。
- 発熱、悪寒、戦慄
- 全身倦怠感
- 頭痛
- 関節痛
- 敗血症:重症化すると、血圧低下や意識障害などを引き起こし、生命に危険が及ぶことがある。
治療・対症療法
蜂窩織炎の治療の基本は、原因菌に対する抗菌薬の投与と、局所の安静・冷却です。
治療
- 抗菌薬投与
- 軽症の場合:セフェム系やペニシリン系の経口抗菌薬が選択されます。
- 中等症〜重症の場合:入院の上、ペニシリン系やセフェム系の抗菌薬を点滴で投与します。MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)が疑われる場合は、抗MRSA薬(バンコマイシン、リネゾリドなど)が使用されます。
- 外科的処置
- 膿瘍(膿のたまり)を形成している場合は、切開して膿を排出する「切開排膿」が必要です。
- 壊死性筋膜炎など、組織の壊死が疑われる場合は、緊急で壊死組織を除去する「デブリードマン」が行われます。
対症療法
- 患肢の安静と挙上
- 炎症の拡大を防ぎ、浮腫を軽減させるために、患肢を安静に保ち、心臓より高い位置に挙上することが非常に重要です。
- 冷却
- 熱感や疼痛を和らげるために、患部を冷やします(クーリング)。ただし、冷やしすぎによる血行障害には注意が必要です。
- 疼痛コントロール
- 痛みが強い場合は、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)などの鎮痛薬を使用します。
- 水分・栄養管理
- 発熱や食欲不振により脱水や栄養不足に陥りやすいため、十分な補液や栄養補給を行います。
看護のポイント
全身状態と局所症状の的確なアセスメント
- バイタルサインの観察:発熱のパターン、血圧低下や頻脈など、敗血症の兆候に注意します。
- 局所症状の観察:発赤、腫脹、熱感、疼痛の範囲と程度を毎日観察し、記録します(マーキングや写真撮影が有効)。症状の拡大・悪化は治療効果が不十分であるサインです。
- 疼痛のアセスメント:NRSなどを用いて痛みの程度を客観的に評価し、鎮痛薬の効果を確認します。
- 検査データのモニタリング:白血球数やCRPなどの炎症マーカーの推移を確認し、治療効果を評価します。
安楽な体位の保持と環境整備
- 患肢の挙上:クッションや枕、専用の挙上台などを用いて、患肢が心臓より高い位置に保たれるように工夫します。患者が安楽に過ごせるよう、体位を調整します。
- 安静の保持:トイレ歩行など、必要最低限の活動に留めてもらうよう説明し、協力を得ます。ナースコールを手の届く範囲に置くなどの環境整備も重要です。
- 冷却:医師の指示のもと、アイスノンなどで患部を冷却します。直接皮膚に当てず、タオルで包むなどして凍傷を防ぎます。
スキンケアと感染管理
- 皮膚の清潔保持:患部以外の皮膚は清潔に保ち、新たな感染源を作らないようにします。
- 水虫(足白癬)のケア:水虫が原因の場合、その治療も並行して行います。患者へのフットケア指導が再発予防につながります。
- 接触感染予防:水疱や浸出液がある場合、標準予防策(スタンダードプリコーション)を徹底し、処置の前後には必ず手指衛生を行います。
退院指導・再発予防教育
蜂窩織炎は再発しやすい疾患です。退院後もセルフケアが継続できるよう、具体的な指導を行います。
- フットケアの重要性:足を毎日観察し、清潔に保つこと、保湿を行い乾燥や亀裂を防ぐことの重要性を伝えます。
- 小さな傷の管理:小さな傷でも放置せず、洗浄・消毒して清潔に保つよう指導します。
- 基礎疾患の管理:糖尿病やリンパ浮腫など、リスクファクターとなる基礎疾患の治療・管理を継続することの重要性を説明します。
- 再発の初期症状:赤み、腫れ、熱感、痛みなど、再発を疑う初期症状が出現したら、すぐに医療機関を受診するよう指導します。
