ラクナ梗塞について徹底解説
 あずかん
あずかん脳梗塞の中でも頻度の高い「ラクナ梗塞」は、臨床現場で出会う機会も多いです。この記事では、ラクナ梗塞の基本的な知識から、具体的な看護のポイントまで、分かりやすく解説します。
ラクナ梗塞とは
ラクナ梗塞は、脳の深い部分にある細い穿通枝動脈が詰まることで起こる、小さな脳梗塞です。梗塞巣の大きさは、直径15mm以下と定義されています。
「ラクナ」とはラテン語で「小さなくぼみ」や「空洞」を意味し、梗塞巣が治癒した後に小さな空洞が残ることから、この名前が付けられました。
穿通枝動脈とは
穿通枝動脈は、太い脳主幹動脈からほぼ直角に分岐し、大脳基底核、視床、内包、脳幹といった脳の深部を栄養しています。これらの部位は、運動機能や感覚機能、意識などを司る重要な役割を担っています。
なぜ詰まるのか
主な原因は、長年の高血圧による「リポヒアリン化」や「微小アテローム」と呼ばれる血管壁の変性です。
リポヒアリン化: 高血圧の持続により、血管壁に硝子様の物質が沈着し、血管がもろく、内腔が狭くなる状態
微小アテローム: 穿通枝動脈の根元に、小さなアテロームが形成され、血管を閉塞させる
これらの変化により血流が途絶え、その先の脳組織が壊死に陥るのが、ラクナ梗塞のメカニズムです。
ラクナ梗塞の主な原因
ラクナ梗塞の最大の危険因子は高血圧です。その他にも、以下のような生活習慣病が深く関わっています。
高血圧: 持続的な血圧の高さが、穿通枝動脈の血管壁にダメージを与え、リポヒアリン化を引き起こす
糖尿病: 高血糖状態は血管内皮を傷つけ、動脈硬化を促進する
脂質異常症(高コレステロール血症): 血液中の悪玉コレステロール(LDL)が血管壁に蓄積し、アテローム硬化の原因となる
喫煙: ニコチンが血管を収縮させ、血圧を上昇させるほか、血管内皮を傷つけ動脈硬化を進行させる
加齢: 年齢とともに血管はしなやかさを失い、動脈硬化が進行しやすくなる
これらの危険因子が複数重なることで、発症リスクはさらに高まります。
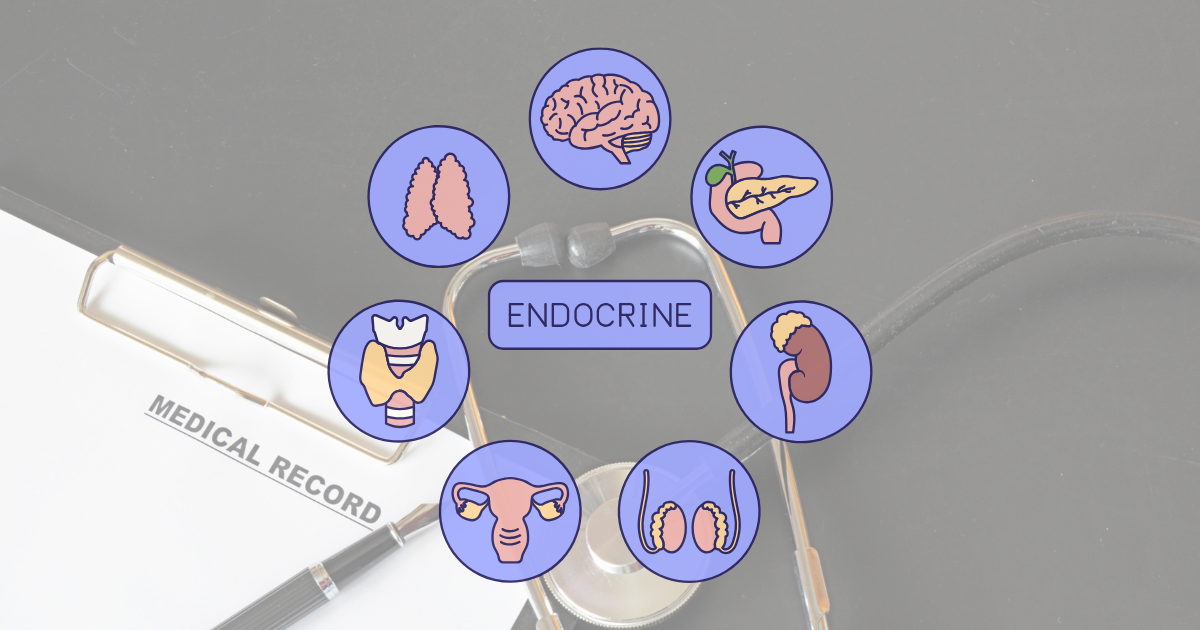
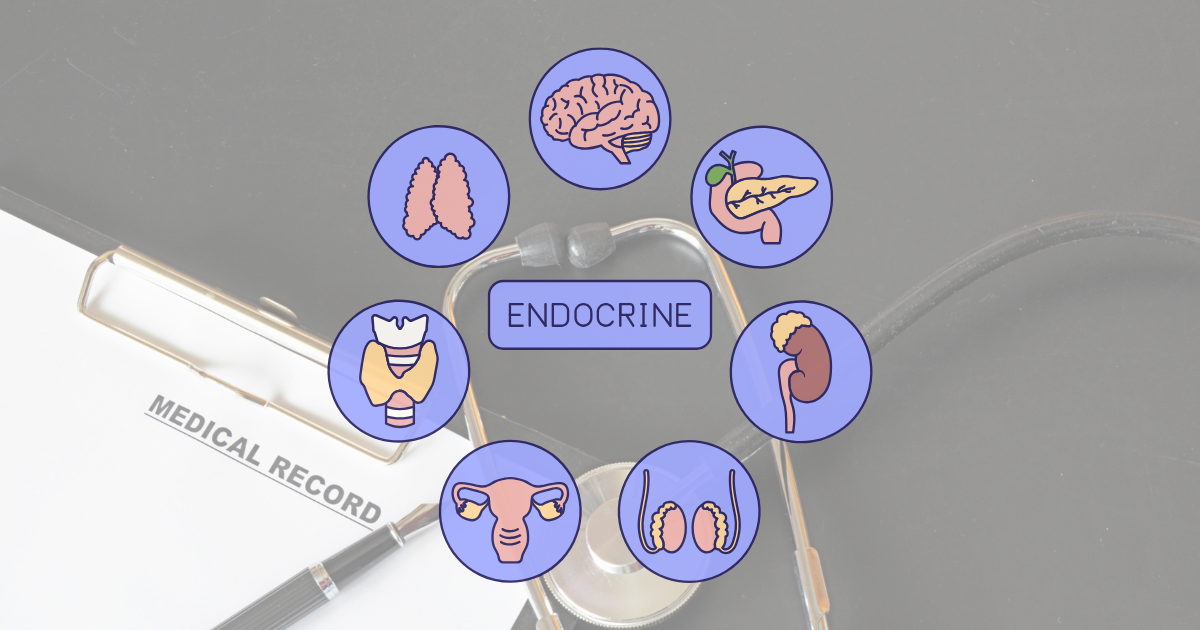
ラクナ梗塞の症状
ラクナ梗塞は梗塞巣が小さいため、症状は比較的軽いことが多いですが、梗塞が起きた部位によって様々な症状が現れます。代表的な5つの症候群があります。
| 症候群 | 主な症状 | 梗塞部位の例 |
|---|---|---|
| 純粋運動性不全麻痺 | 片側の顔面、腕、足の麻痺(感覚障害や失語はない) | 内包後脚 |
| 純粋感覚性脳卒中 | 片側の顔面、腕、足のしびれ感や感覚鈍麻 | 視床 |
| 構音障害・ clumsy hand 症候群 | ろれつが回らない、片方の手がぎこちない | 橋、内包膝部 |
| 運動失調性不全麻痺 | 麻痺側の手足に運動失調(協調運動の障害)がみられる | 橋、内包後脚 |
| 感覚運動性脳卒中 | 純粋運動性不全麻痺と純粋感覚性脳卒中の症状が合併 | 視床、内包 |
これらの症状は、突然出現するのが特徴です。意識障害や失語、失行、半側空間無視といった高次脳機能障害は、通常みられません。
また、症状が軽いからといって軽視は禁物です。無症状の小さな梗塞(無症候性脳梗塞)が多発すると、認知機能の低下やパーキンソニズム(動作緩慢、歩行障害など)の原因となる「多発性脳梗塞」や「血管性認知症」につながる可能性があります。
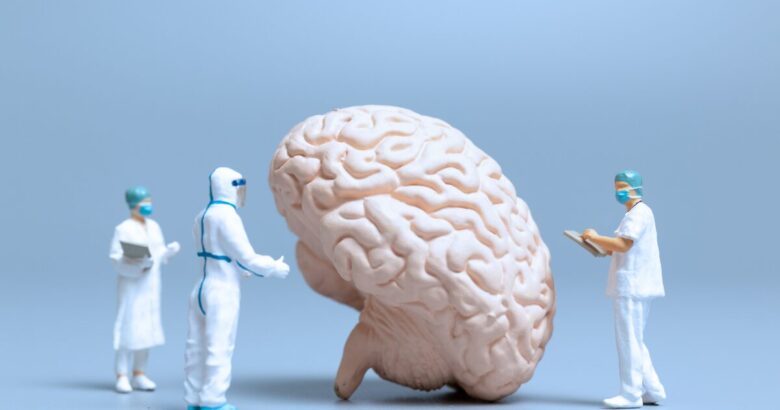
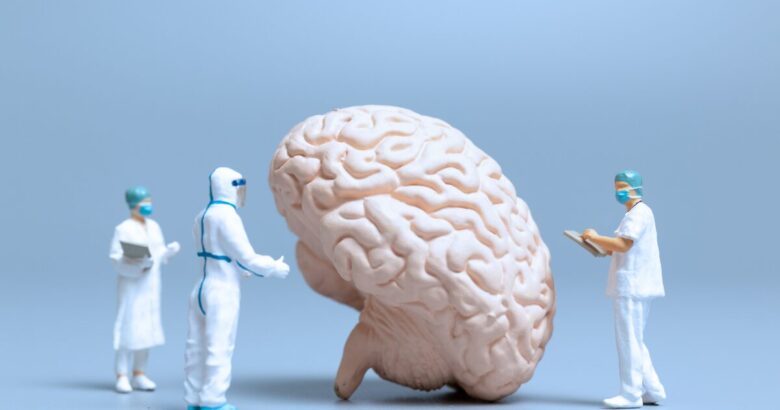
治療・対症療法
急性期治療
発症から4.5時間以内であれば、t-PA(組織プラスミノーゲンアクチベータ)による血栓溶解療法が検討されますが、ラクナ梗塞のような細い血管の閉塞では適応とならない場合も多いです。
多くの場合、以下の薬物療法が中心となります。
抗血小板薬: アスピリンやクロピドグレルなど。血小板が固まるのを防ぎ、血栓が大きくなるのを防ぎます。
脳保護薬: エダラボンなど。脳梗塞によって発生するフリーラジカルを除去し、脳細胞を保護します。
抗浮腫薬: グリセオールなど。脳のむくみ(脳浮腫)を軽減するために使用します。
再発予防(二次予防)
再発予防は、ラクナ梗塞の治療において最も重要です。原因となる生活習慣病の管理が中心となります。
抗血小板薬の継続: 再発予防のために、生涯にわたり服用を続けることが基本です。
降圧薬: 厳格な血圧コントロールが最も重要です。目標値(例:130/80mmHg未満)を維持します。
血糖コントロール: 糖尿病治療薬やインスリンにより、血糖値を適切に管理します。
脂質管理: スタチンなどの脂質異常症治療薬で、コレステロール値をコントロールします。
生活習慣の改善: 禁煙、節度ある飲酒、塩分を控えたバランスの良い食事、適度な運動が推奨されます。
リハビリテーション
麻痺や構音障害などの後遺症に対して、早期からリハビリテーションを開始します。
理学療法(PT): 起き上がり、座位、立位、歩行などの基本的な動作能力の回復を目指します。
作業療法(OT): 食事、更衣、排泄などの日常生活動作(ADL)や、より高度な応用的動作(IADL)の訓練を行います。
言語聴覚療法(ST): 構音障害や嚥下障害(飲み込みの障害)に対する評価と訓練を行います。
看護のポイント
急性期の看護:状態変化の早期発見
- バイタルサインの観察
特に血圧の変動に注意します。医師の指示範囲内にコントロールされているか、頻回に確認します。 - 神経学的所見の観察
意識レベル(JCS/GCS)、瞳孔所見、麻痺の程度や範囲の変化を注意深く観察し、症状の増悪を早期に発見します。 - 安全・安楽の確保
麻痺による転倒・転落リスクをアセスメントし、ベッド柵の使用や離床センサーの活用など、環境整備を行います。
再発予防に向けた生活習慣指導
患者自身が再発予防の重要性を理解し、主体的に治療に取り組めるよう支援することが、看護師の重要な役割です。
- 服薬管理と指導
降圧薬や抗血小板薬の役割、副作用について分かりやすく説明し、自己中断しないよう指導します。お薬カレンダーや一包化の提案も有効です。 - 血圧管理の指導
家庭での血圧測定の重要性と、正しい測定方法(朝晩2回、座位で安静後など)を指導します。測定した血圧を記録する習慣づけを支援します。 - 食事・水分管理
栄養士と連携し、減塩食の必要性や、具体的な調理の工夫を説明します。脱水は血液を濃縮させ、脳梗塞を誘発するため、適切な水分摂取を促します。 - 嚥下機能の評価と食事介助
構音障害がある場合、嚥下障害を合併している可能性があります。食事前に嚥下機能のスクリーニング(反復唾液嚥下テストなど)を行い、必要に応じて食事形態の調整や、STへのコンサルトを検討します。食事中は、一口量の調整や交互嚥下を促し、誤嚥に注意します。
ADLの自立に向けた支援
早期離床とリハビリテーションへの参加を促し、残存機能を最大限に活用して、ADLの自立を目指します。
- セルフケアの促進
麻痺があっても、できることは自分で行ってもらうよう促します。自助具の紹介や、更衣・整容の工夫(前開きの服、マジックテープの活用など)を多職種と連携して検討します。 - 排泄の自立支援
トイレまでの動線を確認し、手すりの設置やポータブルトイレの活用を検討します。麻痺側への注意を促し、安全な移乗動作を指導します。
精神的・社会的支援
突然の発症による不安や、後遺症への焦りなど、患者の心理的側面に寄り添うことも大切です。
- 傾聴と共感
患者や家族の思いを傾聴し、不安を受け止め、共感的な態度で接します。 - 退院支援
自宅の環境や介護者の状況を考慮し、MSWやケアマネジャーと連携して、退院後の生活を見据えた支援(介護保険サービスの調整、住宅改修の提案など)を早期から開始します。