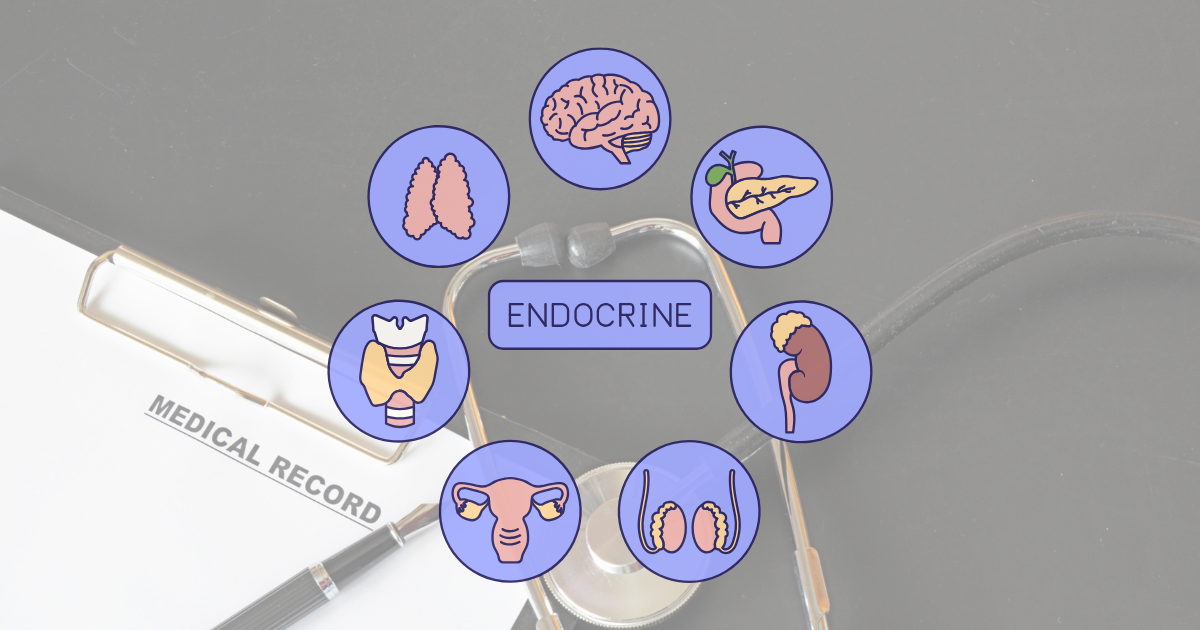甲状腺機能亢進症について徹底解説
 あずかん
あずかん甲状腺機能亢進症は、内分泌疾患の中でも遭遇する機会の多い病態です。患者さんのQOLに大きく影響するため、看護師として病態を深く理解し、適切なケアを提供することが求められます。この記事では、甲状腺機能亢進症の基本から臨床で役立つ看護のポイントまで、分かりやすく解説します。
目次
甲状腺機能亢進症について
甲状腺機能亢進症は、甲状腺ホルモン(サイロキシン:T4、トリヨードサイロニン:T3)が過剰に分泌されることで、全身の代謝が異常に活発になる状態(甲状腺中毒症)を指します。
イメージとしては、代謝のアクセルが踏みっぱなしの状態と言えます。
全身の臓器が常にフル稼働している状態のため、心臓は常に速く動き、エネルギー消費も激しくなります。この状態が続くと、心臓への負担が増加し、不整脈や心不全を引き起こすリスクが高まります。また、自律神経のバランスも乱れ、精神的にも不安定になりやすいのが特徴です。
甲状腺機能亢進症の原因
| 原因疾患 | 特徴 |
|---|---|
| バセドウ病 | 自己免疫疾患の一つで、甲状腺機能亢進症の最も一般的な原因です。本来は体を守るはずの免疫が、甲状腺を刺激する自己抗体(TSH受容体抗体:TRAb)を作り出します。この抗体が甲状腺を過剰に刺激し続けることで、甲状腺ホルモンが大量に分泌されます。 |
| プランマー病(中毒性多結節性甲状腺腫) | 甲状腺にできた複数の結節(しこり)が、自律的に甲状腺ホルモンを過剰産生する病気です。高齢者に多く見られます。 |
| 亜急性甲状腺炎 | ウイルス感染などがきっかけとなり、甲状腺組織が破壊されることで、一時的に蓄えられていた甲状腺ホルモンが血液中に漏れ出す状態です。通常は自然に回復します。 |
| 無痛性甲状腺炎 | 自己免疫的な機序が考えられており、痛みなく甲状腺組織が破壊され、一時的にホルモンが漏れ出します。出産後の女性にみられることがあります。 |
甲状腺機能亢進症の主な症状
甲状腺ホルモンは全身の代謝を司るため、その症状は多岐にわたります。身体的症状だけでなく、精神的症状にも注意深く観察することが重要です。
身体的症状
- 循環器系: 頻脈(1分間に100回以上)、動悸、息切れ、心房細動などの不整脈、高血圧
- 全身症状: 体重減少(食欲は旺盛なのに痩せる)、発汗過多、暑がり(異常な暑がり)、微熱、倦怠感
- 消化器系: 食欲亢進、軟便・下痢、口渇
- 神経・筋系: 手指の振戦(ふるえ)、筋力低下、集中力低下
- 皮膚・毛髪: 皮膚の湿潤、脱毛
- 眼球症状(バセドウ病に特有): 眼球突出、複視(物が二重に見える)、眼の痛み
精神的症状
- イライラ、落ち着きのなさ(易刺激性)
- 不眠
- 気分の落ち込み
- 不安感
治療と対症療法
治療の主な目的は、過剰な甲状腺ホルモンの分泌を抑え、正常な状態に戻すことです。
治療法は主に3つあり、患者の年齢、症状、社会的背景などを考慮して選択されます。
| 治療法 | 内容 | メリット | デメリット・副作用 |
|---|---|---|---|
| 薬物療法(抗甲状腺薬) | 甲状腺ホルモンの合成を抑える薬(チアマゾール、プロピルチオウラシル)を内服します。治療の第一選択となることが多いです。 | ・外来で治療が可能 ・甲状腺機能を温存できる | ・治療が長期にわたる ・副作用(無顆粒球症、肝機能障害、皮疹など)のリスク |
| アイソトープ(放射性ヨウ素)治療 | 放射性ヨウ素を含むカプセルを内服します。ヨウ素が甲状腺に取り込まれる性質を利用し、放射線で甲状腺細胞を破壊してホルモン産生を減らします。 | ・治療効果が高い ・薬物療法で効果が得られない場合や副作用で継続できない場合に有効 | ・甲状腺機能低下症になる可能性が高い ・治療後、妊娠・授乳に制限がある |
| 手術療法(甲状腺亜全摘術) | 甲状腺の一部または大部分を外科的に切除し、ホルモン産生量を物理的に減らします。 | ・短期間で確実な効果が得られる ・甲状腺腫が大きい場合や、がんの合併が疑われる場合に選択される | ・入院が必要 ・手術合併症(反回神経麻痺による嗄声、副甲状腺機能低下症によるテタニー)のリスク |
対症療法
頻脈や動悸などの症状が強い場合には、交感神経の働きを抑えるβ遮断薬が併用されます。
看護のポイント
安静を保てる環境調整と身体的苦痛の緩和
- 安静の確保
代謝が亢進しているため、心臓に負担がかかっています。心拍数や血圧をモニタリングし、必要に応じて活動制限を促し、安静を保てる静かな環境を提供します。 - 体温管理
暑がりで発汗が多いため、室温を低めに設定したり、寝具を調整したりして安楽に過ごせるよう援助します。 - 栄養管理
エネルギー消費が激しく体重が減少しやすいため、高カロリー・高タンパクの食事を摂取できるよう栄養指導を行います。患者の嗜好に合わせ、少量で栄養価の高い間食を取り入れるなどの工夫も有効です。
精神的サポートとコミュニケーション
- 共感的な態度
イライラしたり落ち着きがなかったりするのは、病気による症状であることを理解し、患者の言動を傾聴し、共感的な態度で接します。家族にも病状について説明し、理解と協力を求めます。 - 不安の軽減
治療や予後に対する不安を傾聴し、正しい情報を提供して意思決定を支援します。
薬物療法の管理と副作用のモニタリング
- 確実な与薬
内服は治療の基本です。服薬の重要性を説明し、アドヒアランス(患者が治療方針の決定に賛同し積極的に治療を受けること)を高める支援をします。 - 副作用の早期発見
特に注意すべき副作用は無顆るい球症です。突然の高熱や咽頭痛は初期症状の可能性があるため、これらの症状が見られたらすぐに医師や看護師に報告するよう指導します。定期的な血液検査の重要性も説明します。
眼球症状のケア(バセドウ病)
- 眼の保護
眼球突出により眼が閉じにくくなる場合、乾燥や角膜の損傷を防ぐために点眼薬の使用や、就寝時に眼帯で保護するなどのケアが必要です。 - 複視への対応
物が二重に見える場合は、転倒リスクが高まります。療養環境を整備し、安全を確保します。
退院指導とセルフケア支援
- 規則正しい生活
過労やストレスは症状を悪化させる可能性があるため、規則正しい生活と十分な休息の重要性を指導します。 - 定期的な受診の徹底
治療は長期にわたるため、自己判断で服薬を中断しないよう、定期的な受診と検査の必要性を繰り返し説明します。 - 食事
ヨウ素の過剰摂取は、病状に影響を与える可能性があるため、昆布などのヨウ素を多く含む食品の大量摂取は避けるよう指導します。(特にアイソトープ治療前は厳密なヨウ素制限が必要です)