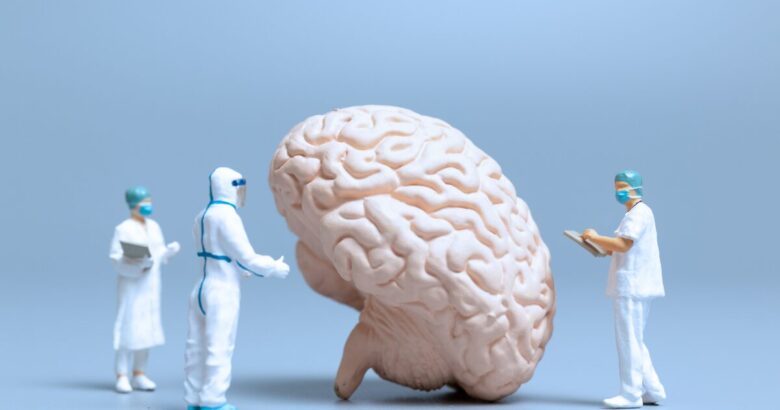前頭側頭型認知症(FTD)の病態から看護のポイントまで徹底解説
 あずかん
あずかん前頭側頭型認知症(FTD)は、脳の前頭葉と側頭葉が萎縮することで発症する認知症の一種です。アルツハイマー型認知症とは異なり、初期には記憶障害よりも人格の変化や行動障害、言語障害が目立つことが特徴です。若年で発症することも少なくありません。
この記事では、適切なケアを提供できるよう、病態生理から具体的な看護のポイントまでを分かりやすく解説します。
目次
前頭側頭型認知症について
前頭側頭型認知症は、脳の前頭葉と側頭葉前方が選択的に萎縮(変性・脱落)することで発症します。この萎縮は、異常なタンパク質(主にTDP-43またはタウタンパク)が神経細胞内に蓄積することが原因で引き起こされると考えられています。
前頭葉の機能: 思考、判断、感情のコントロール、理性、社会的な行動などを司ります。
側頭葉の機能: 言語の理解、記憶、聴覚などを司ります。
これらの領域が障害されることで、FTD特有の症状が現れます。アルツハイマー型認知症が主に記憶を司る海馬や頭頂葉から萎縮が始まるのと対照的です。
前頭側頭型認知症の原因
FTDの明確な原因はまだ完全には解明されていませんが、異常タンパク質の蓄積が神経細胞死を引き起こすという点が指摘されています。
- 異常タンパク質の蓄積
- タウタンパク: 神経細胞の骨格を安定させる役割を持つタウタンパクが異常にリン酸化され、蓄積することで神経原線維変化を形成します。これはピック病とも呼ばれます。
- TDP-43: 核内でDNAやRNAの代謝に関わるTDP-43というタンパク質が、細胞質内に異常に蓄積するタイプです。
- FUS: FUSというタンパク質が異常に蓄積する、まれなタイプも存在します。
- 遺伝的要因
- FTDの約3分の1から半数に家族歴があると言われており、遺伝的要因が関与するケースも少なくありません。原因遺伝子として、MAPT遺伝子、GRN遺伝子、C9orf72遺伝子などが同定されています。
前頭側頭型認知症の症状
FTDの症状は、脳の萎縮部位によって大きく3つのタイプに分けられます。
行動障害型前頭側頭型認知症 (bvFTD)
最も一般的なタイプで、前頭葉の萎縮が主体となります。
- 人格の変化・社会的行動の障害
- 脱抑制: 社会的なルールを無視した行動(万引き、暴力など)、思ったことをすぐ口にする。
- 無関心・アパシー: 何事にも興味や関心を示さなくなり、自発性が低下する。身だしなみを気にしなくなる。
- 共感の欠如: 他人の感情を理解したり、配慮したりすることが難しくなる。
- 常同行動
- 同じ時間に同じ道を散歩する(時刻表的生活)、同じ言葉を繰り返す、手を叩き続けるなど、決まりきった行動を繰り返します。
- 食行動異常
- 甘いものばかりを好んで食べる、過食、食事のマナーが悪くなるなどの変化が見られます。
意味性認知症 (SD)
側頭葉(特に左側優位)の萎縮が主体となります。
- 意味記憶の障害
- 言葉の意味が分からなくなります。「これは何?」と聞かれても物の名前が出てこない(語義失語)。
- 人の顔や物の認識が困難になります。
- 行動
- 行動障害型と同様に、常同行動が見られることがあります。
進行性非流暢性失語 (PNFA)
前頭葉の言語野(左側優位)の萎縮が主体となります。
- 言語の障害
- 話し方がぎこちなく、努力を要するようになる(非流暢な発話)。
- 文法的な間違いが多くなる(失文法)。
- 言葉を聞いて理解することは比較的保たれます。
治療・対症療法
現時点でFTDを根治させる治療法はありません。そのため、症状を緩和し、生活の質(QOL)を維持するための対症療法が中心となります。
- 薬物療法
- アルツハイマー型認知症の治療薬(コリンエステラーゼ阻害薬など)は、FTDの症状を悪化させる可能性があるため、原則として使用しません。
- 行動障害(易怒性、攻撃性、脱抑制など)に対しては、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)などの抗うつ薬や、非定型抗精神病薬が少量用いられることがあります。しかし、副作用に注意しながら慎重な投与が必要です。
- 非薬物療法
- 環境調整: 患者が安心して穏やかに過ごせるように、刺激の少ない静かな環境を整えることが重要です。危険なものは片付け、生活空間をシンプルにします。
- リハビリテーション:
- 言語聴覚療法: 失語症状のある患者に対して、コミュニケーションを支援する訓練を行います。
- 作業療法: 日常生活動作(ADL)を維持・向上させるための訓練や、本人が楽しめる活動を取り入れます。
- 介護保険サービスの活用: デイサービスやショートステイなどを利用し、介護者の負担を軽減することも大切です。
看護のポイント
安全の確保と環境調整
- 危険の予測と予防
- 脱抑制や判断力の低下により、予期せぬ行動(急に飛び出す、危険な物を口にするなど)をとる可能性があります。常に患者の行動を観察し、危険を予測して事故を未然に防ぐ環境を整えます(例:刃物や火元の管理、ドアの施錠)。
- 刺激の少ない環境
- 患者が混乱しないよう、静かで落ち着いた環境を提供します。テレビの音量や人の出入りにも配慮しましょう。
コミュニケーションの工夫
- 病気による症状であることを理解する
- 患者の反社会的な行動や無関心な態度は、病気による症状であり、本人の意図ではないことを常に念頭に置きます。感情的に対応せず、冷静に受け止める姿勢が重要です。
- シンプルで具体的な言葉かけ
- 指示や質問は、短く、分かりやすい言葉で伝えます。「あれ」「これ」などの指示語は避け、具体的に伝えます(例:「お風呂に入りましょう」ではなく、「〇〇さん、服を脱いで、お風呂に入りますよ」)。
- 非言語的コミュニケーションの活用
- 言語障害がある患者には、ジェスチャーや絵、写真などを用いると伝わりやすいことがあります。穏やかな表情や口調で接することも安心感につながります。
- 否定しない、叱責しない
- 患者の行動を頭ごなしに否定したり、叱ったりすると、不安や混乱を招き、症状が悪化することがあります。危険がない限りは見守り、関心を別のことに向ける(ディストラクション)などの対応が有効です。
常同行動・食行動異常への対応
- 常同行動への対応
- 危険がなく、他人に迷惑をかけない常同行動は、無理に止めさせず、本人のペースを尊重します。ルーティンを把握し、ケアの計画に組み込むことで、患者の不安を軽減できます。
- 食行動異常への対応
- 過食や異食を防ぐため、手の届く場所に食べ物を置かないようにします。栄養バランスが偏らないよう、食事内容を工夫し、時間を決めて提供します。食事のマナーが悪くなっても、自尊心を傷つけないように配慮し、必要に応じて介助します。
家族への支援
- 疾患教育
- FTDという病気について家族に十分に説明し、患者の変化が病気の症状であることを理解してもらうことが、虐待の防止や介護負担の軽減につながります。
- 介護負担の傾聴と共感
- 介護者は、理解されにくい症状に悩み、精神的・身体的に疲弊していることが多いです。その苦労を傾聴し、共感する姿勢を示し、信頼関係を築きます。
- 社会的資源の情報提供
- 介護保険サービスや地域の相談窓口、患者会・家族会などの社会資源について情報提供し、家族が孤立しないように支援します。レスパイトケア(介護者の休息)の重要性も伝えましょう。