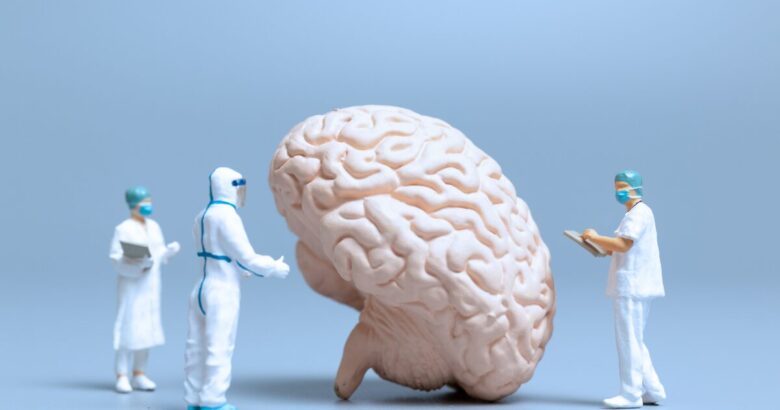血管性認知症の病態から看護のポイントまで徹底解説
 あずかん
あずかん認知症の中でも、アルツハイマー型に次いで多いとされる血管性認知症。脳血管障害をきっかけに発症するため、再発予防や生活習慣の改善が非常に重要となります。
この記事では、血管性認知症の病態生理から原因、症状、治療法、そして最も重要な看護のポイントまで、詳しく解説します。
血管性認知症とは
血管性認知症は、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血といった脳血管障害によって、脳の神経細胞に酸素や栄養が供給されなくなり、その細胞が死んでしまうことで発症します。脳のどの部分がダメージを受けるかによって、現れる症状が異なるのが大きな特徴です。
障害された脳の機能は回復が難しく、脳血管障害が再発するたびに段階的に症状が進行していきます。
血管性認知症の原因
血管性認知症の直接的な原因は脳血管障害ですが、その引き金となるのは以下のような生活習慣病です。
高血圧
糖尿病
脂質異常症(高脂血症)
心疾患(特に心房細動)
喫煙
肥満
これらの危険因子は、動脈硬化を促進し、脳の血管を詰まらせたり(脳梗塞)、破れやすくしたり(脳出血)する原因となります。
血管性認知症の症状
血管性認知症の症状は、障害された脳の部位によって様々であり、個人差が大きいのが特徴です。そのため、「まだら認知症」とも呼ばれます。記憶障害が目立つアルツハイマー型認知症とは異なり、一部の認知機能は保たれていることが多いです。
主な症状
認知機能障害: 遂行機能障害(計画を立てて実行できない)、注意障害、失語、失行、失認など。
運動症状: 歩行障害、麻痺、嚥下障害、構音障害など、脳血管障害の後遺症として現れます。
精神症状・感情の変化: 感情失禁(急に泣いたり怒ったりする)、意欲・自発性の低下、抑うつ気分などが見られやすいです。
治療・対症療法
一度壊死してしまった脳細胞を元に戻す治療法は、現在のところありません。そのため、治療の主な目的は、脳血管障害の再発予防と症状のコントロールになります。
- 薬物療法
- 再発予防: 高血圧、糖尿病、脂質異常症などの基礎疾患に対する治療薬(降圧薬、血糖降下薬、抗血小板薬、抗凝固薬など)が中心となります。
- 症状の改善: 認知機能改善薬や、意欲低下、抑うつ、攻撃性などの周辺症状(BPSD)を緩和する向精神薬が用いられることがあります。
- 非薬物療法(リハビリテーション)
- 理学療法・作業療法: 残された身体機能や認知機能を最大限に活用し、日常生活動作(ADL)の維持・向上を目指します。
- 言語聴覚療法: 失語症や構音障害、嚥下障害に対する訓練を行います。
看護のポイント
再発予防のための生活習慣指導と管理
バイタルサインのモニタリング
血圧、脈拍、血糖値などを定期的に測定し、異常の早期発見に努めます。
服薬管理
処方された薬剤を確実に内服できるよう、服薬カレンダーの活用や家族への指導など、患者の状況に合わせた支援を行います。
食事・運動指導
減塩食やバランスの取れた食事、適度な運動習慣が身につくよう、継続的に関わります。
ADLの維持・向上と安全確保
リハビリテーションの継続支援
患者の意欲を引き出し、リハビリを継続できるよう声かけや環境整備を行います。
転倒・転落予防
麻痺や歩行障害がある場合が多いため、ベッド周囲の環境整備や適切な福祉用具の選定、見守りなどを行います。
嚥下障害への対応
食事形態の調整や食事介助の方法を工夫し、誤嚥性肺炎を予防します。
精神的・心理的サポート
感情失禁への理解と対応
感情の急な変化は病気によるものであることを理解し、冷静に受け止め、患者の気持ちが落ち着くのを待ちます。
意欲低下へのアプローチ
無理強いはせず、患者が興味を持てるような活動(趣味など)を取り入れ、小さな成功体験を積み重ねられるよう支援します。
家族への支援
介護者である家族も大きな不安や負担を抱えています。家族の思いに耳を傾け、介護サービスの利用を促すなど、社会資源の情報提供も重要です。