浮腫の観察項目とその根拠を徹底解説!
 あずかん
あずかん看護の現場で頻繁に遭遇する「浮腫」。単なる「むくみ」と捉えがちですが、その背後には心不全、腎不全、肝硬変、低栄養など、様々な病態が隠れている可能性があります。的確なアセスメントとケアにつなげるためには、浮腫を正しく観察し、その意味を理解することが不可欠です。
この記事では、自信を持って浮腫のケアにあたれるよう、観察項目とその根拠を詳しく解説します。
目次
浮腫の観察項目とアセスメントの根拠
| 観察項目(WHAT) | 根拠(WHY) |
|---|---|
| 1. 浮腫の部位と範囲 | |
| – 全身性か局所性か | 全身性の浮腫は、心臓、腎臓、肝臓などの内臓疾患や、低アルブミン血症が原因で起こることが多いです。 局所性の浮腫は、特定の部位の静脈・リンパ管の還流障害(DVT、リンパ浮腫)、炎症、血管透過性の亢進(アレルギーなど)が考えられます。 |
| – 身体のどの部分か(顔、四肢、体幹など) | 重力の影響で、下腿や仙骨部など低い部位に現れやすいです(重力依存性浮腫)。 心不全では下肢に、腎不全では顔面(特に眼瞼)に現れやすいという特徴もあります。 腹水や胸水も体内の水分貯留であり、広義の浮腫と捉えられます。 |
| 2. 圧痕性浮腫の程度 | |
| – 指で圧迫し、くぼみが残るか | 圧迫によって間質液が移動し、くぼみ(圧痕)が残る状態を圧痕性浮腫と呼びます。これは、間質液の貯留が主な原因であることを示唆します。 |
| – 圧痕の深さと回復時間 | 圧痕の程度をスケールで評価することで、浮腫の重症度を客観的に記録し、経時的な変化を把握できます。 +1: わずかなくぼみ、すぐに戻る +2: 4mm程度のくぼみ、10-15秒で戻る +3: 6mm程度のくぼみ、1分以上続く +4: 8mm程度のくぼみ、2分以上続く |
| 3. 皮膚の状態 | |
| – 皮膚の色、湿潤、乾燥 | 循環不全により皮膚が蒼白になったり、チアノーゼが見られることがあります。 皮膚が薄く伸展し、テカテカと光って見えることがあります(菲薄化・緊満)。 間質液が漏れ出し、湿潤している場合は、感染のリスクが非常に高くなります。 |
| – 皮膚の損傷、水疱、びらんの有無 | 浮腫のある皮膚は、わずかな刺激で傷つきやすくなっています(脆弱化)。 水疱形成や皮膚の亀裂は、感染の入り口となるため、特に注意が必要です。 |
| 4. 体重と水分出納 | |
| – 体重の増減(毎日同じ条件で測定) | 体重は、体内の水分貯留量を最も客観的に示す指標です。1kgの体重増加は、約1Lの水分貯留に相当します。 急激な体重増加は、心不全や腎不全の増悪を示唆する重要なサインです。 |
| – In-Outバランス | In(飲水、食事、輸液など)とOut(尿、便、不感蒸泄など)のバランスを評価し、水分が体内に過剰に蓄積していないかを確認します。 |
| 5. バイタルサイン | |
| – 血圧、脈拍、呼吸数、SpO2 | 頻脈や血圧の上昇は、循環血液量の増加(心臓への負荷増大)を示唆します。 呼吸困難や頻呼吸、SpO2の低下は、肺うっ血や胸水の可能性を示唆します。 |
| 6. 随伴症状 | |
| – 呼吸困難、息切れ、咳、痰 | 肺水腫(肺の間質に水がたまる状態)の徴候です。特に、横になると息苦しくなる起坐呼吸は、心不全の重要なサインです。 |
| – 尿量の減少、尿の色 | 腎機能低下による水分排泄の遅延が考えられます。 |
| – 倦怠感、食欲不振 | 全身的な循環不全や、原因疾患による症状として現れます。 |
| 7. 検査データ | |
| – 血清アルブミン値 | 低アルブミン血症(基準値:約4.0-5.0 g/dL)では、血管内に水分を保持する力(膠質浸透圧)が低下し、水分が間質に漏れ出して浮腫が起こります。肝硬変やネフローゼ症候群、低栄養でみられます。 |
| – BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド) | 心臓に負荷がかかると分泌されるホルモンです。BNPの高値は、心不全の重症度を評価する指標となります。 |
| – 腎機能データ(BUN、Cr) | 腎機能の低下は、水分やナトリウムの排泄障害を引き起こし、浮腫の直接的な原因となります。 |
ポンコツ看護師の勉強ログ

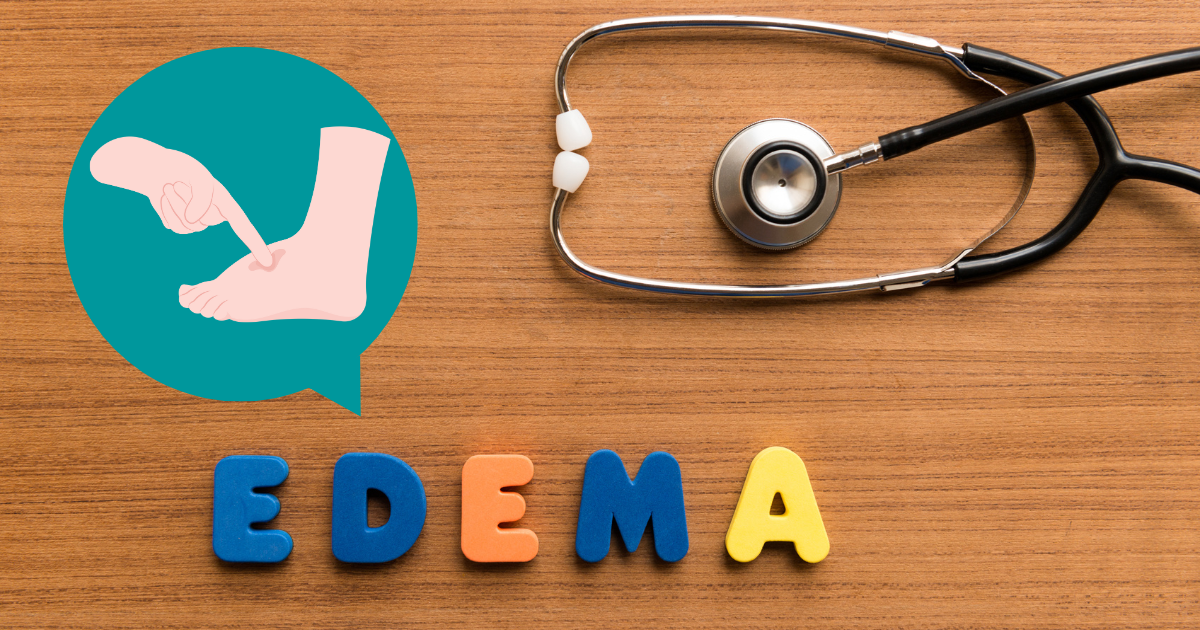
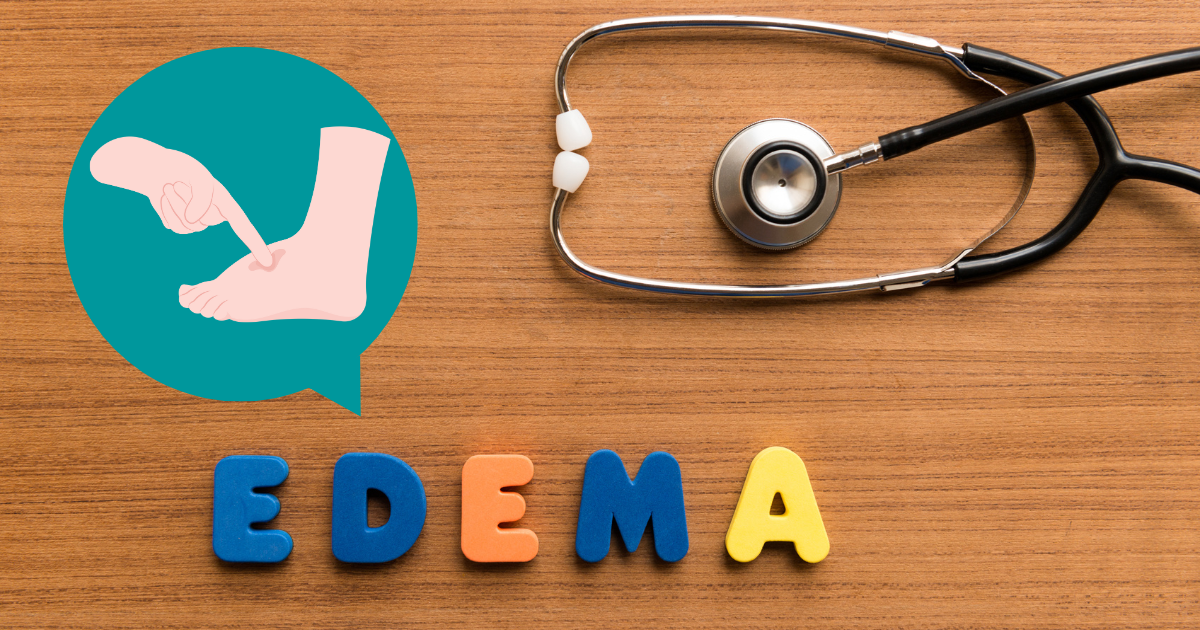
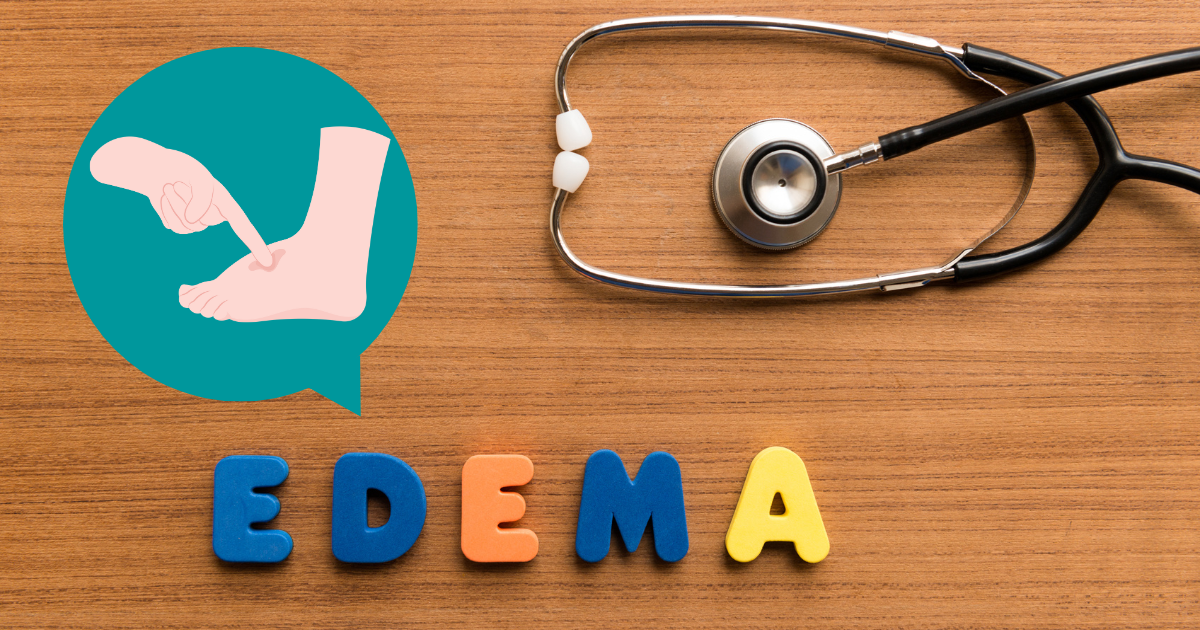
浮腫について | ポンコツ看護師の勉強ログ
臨床で頻繁に遭遇する「浮腫」。なぜ起こるの?どう看護すればいい?そんな新人看護師や看護学生の疑問に答えます。浮腫の病態生理(スターリングの法則)から、圧痕の評価…