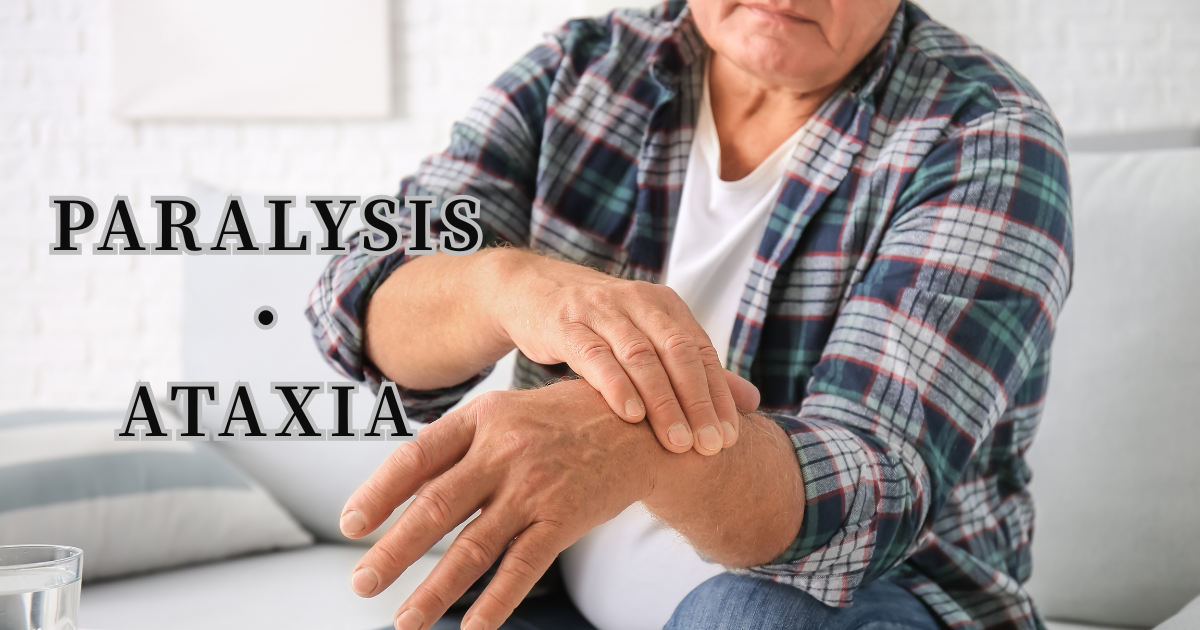運動麻痺・運動失調の病態から看護のポイントまで徹底解説
 あずかん
あずかん運動麻痺や運動失調は、脳卒中や神経変性疾患など、様々な原因で生じる症状であり、患者さんの日常生活に大きな影響を与えます。私たち看護師は、これらの症状を持つ患者さんに対し、正確な知識に基づいたアセスメントと、個別性のある看護計画を立案・実践することが求められます。
この記事では、運動麻痺と運動失調の基本である病態生理から、具体的な看護のポイントまでを分かりやすく解説します。
目次
運動麻痺・運動失調とは
運動麻痺
運動麻痺は、体を動かすための神経経路(錐体路)のどこかが障害されることによって、筋肉の随意運動(自分の意思で行う運動)が困難になる状態を指します。
- 錐体路とは
- 大脳皮質の運動野から始まり、脳幹、脊髄を通って筋肉へ指令を伝える主要な神経路です。この経路が障害されると、脳からの「動け」という指令が筋肉に届かなくなり、麻痺が生じます。
- 上位運動ニューロンと下位運動ニューロン
- 上位運動ニューロン障害: 大脳皮質から脊髄までの障害。筋肉は硬くなる(痙性麻痺)傾向があり、深部腱反射が亢進します。代表的なものに脳卒中があります。
- 下位運動ニューロン障害: 脊髄から末梢神経、筋肉までの障害。筋肉はだらんと弛緩する(弛緩性麻痺)傾向があり、筋萎縮や線維束性収縮が見られます。ギラン・バレー症候群などがこれにあたります。
運動失調
運動失調は、運動麻痺がないにもかかわらず、運動の協調性やバランスが障害される状態です。これは主に、小脳や深部感覚を伝える後索路の障害によって引き起こされます。
- 小脳の役割
- 小脳は、手足の動きの滑らかさ、力の加減、速さの調節、体の平衡感覚を保つといった「調整役」を担っています。
- 小脳の障害
- 小脳が障害されると、運動のプログラムは作れても、それをスムーズに実行できなくなります。例えば、コップを取ろうとすると、手が震えてしまったり、行き過ぎてしまったりします(測定障害)。また、歩行時に足がもつれてふらつく(体幹失調)などの症状が現れます。
- 深部感覚障害
- 自分の手足が今どこにあるか、どのくらい曲がっているかといった位置覚(深部感覚)が障害されることでも、運動失調(感覚性失調)が起こります。この場合、視覚で動きを補おうとするため、目を開けているとある程度できますが、目を閉じると途端に不安定になるのが特徴です。
麻痺は「動かせない」、失調は「うまく動かせない」とイメージすると理解しやすいです。
原因疾患
運動麻痺と運動失調を引き起こす代表的な疾患は以下の通りです。
| 症状 | 主な原因疾患 |
|---|---|
| 運動麻痺 | 脳血管障害: 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血 脳腫瘍: 原発性、転移性 神経変性疾患: 筋萎縮性側索硬化症(ALS) 脊髄疾患: 脊髄損傷、脊髄腫瘍、椎間板ヘルニア 末梢神経障害: ギラン・バレー症候群、糖尿病性神経障害 感染症: 脳炎、髄膜炎 |
| 運動失調 | 脳血管障害: 小脳梗塞、小脳出血 変性疾患: 脊髄小脳変性症、多系統萎縮症 脳腫瘍: 小脳や脳幹の腫瘍 中毒: アルコール中毒、薬物中毒 ビタミン欠乏症: ビタミンB1欠乏症(ウェルニッケ脳症) 自己免疫疾患: 多発性硬化症 |
主な症状
運動麻痺の主な症状
- 単麻痺: 片方の腕または脚のみの麻痺
- 片麻痺: 体の左右どちらか一方の上肢・下肢の麻痺
- 対麻痺: 両方の下肢の麻痺
- 四肢麻痺: 両方の上肢・下肢の麻痺
- 顔面神経麻痺: 顔の筋肉の麻痺
- 構音障害: 呂律が回らない
- 嚥下障害: 飲み込みにくい
運動失調の主な症状
- 体幹失調: 立ったり座ったりしている時に体が揺れる。歩行が不安定(酩酊様歩行)。
- 測定障害: 目標物に対して手や指が通り過ぎたり、届かなかったりする。
- 変換運動障害: 素早く反復する動き(例:手のひらを返したりする動き)ができない。
- 協調運動障害: 複数の筋肉を同時に使う協調した動きがぎこちなくなる。
- 企図振戦: 目標に近づけようとすると、手が震える。
- 眼振: 眼球が意図せず揺れ動く。
- 構音障害: 発語のリズムが乱れ、言葉が途切れ途切れになる(断綴性言語)。
治療・対症療法
治療の基本は、原因疾患の治療です。それに加え、症状を緩和し、ADLの維持・向上を目指す対症療法が行われます。
- 薬物療法
- 痙縮(筋肉のつっぱり)に対して: 筋弛緩薬(バクロフェン、チザニジンなど)、ボツリヌス毒素療法
- 振戦(ふるえ)に対して: β遮断薬、抗てんかん薬
- リハビリテーション
- 理学療法(PT): 関節可動域訓練、筋力増強訓練、基本動作訓練(寝返り、起き上がり、座位、立位)、歩行訓練、装具の検討など。
- 作業療法(OT): 食事、更衣、整容などの日常生活動作訓練、高次脳機能障害へのアプローチ、福祉用具(自助具)の選定・使用訓練。
- 言語聴覚療法(ST): 嚥下機能評価・訓練、構音訓練、コミュニケーション手段の確保。
- 外科的治療
- 原因となっている脳腫瘍や血腫の除去。
看護のポイント
運動麻痺・運動失調のある患者への看護では、「安全の確保」と「残存機能の活用・自立支援」が大きな柱となります。
安全確保:転倒・転落、合併症の予防
- 転倒・転落予防
- 患者の麻痺・失調の程度を正確にアセスメントし、移動・移乗時の介助方法を統一する。
- ベッド周囲の環境整備(不要なものを置かない、床を濡らさない、適切な高さのベッド)。
- ナースコールは患者の届く位置に必ず設置し、使用方法を説明する。
- 履き物は滑りにくく、足に合ったものを選ぶ。
- 必要に応じてセンサーマットなどを使用する。
- 皮膚トラブルの予防(褥瘡予防)
- 麻痺側は自力での体位変換が困難なため、定期的な体位変換を計画的に行う。
- 骨突出部の観察、皮膚の湿潤や汚染に注意し、清潔を保つ。
- 体圧分散寝具の活用を検討する。
- 関節拘縮の予防
- 麻痺側の関節可動域訓練(ROM訓練)を、リハビリスタッフと連携して行う。
- 良肢位(機能的肢位)を保つためのクッション活用。
- 誤嚥性肺炎の予防
- 食事の際は、覚醒レベルが良い状態で、上半身を起こした姿勢(90度が理想)をとる。
- 食事形態やとろみの必要性をSTと連携してアセスメントする。
- 一口量やペースを観察し、むせがないか注意する。
- 食後の口腔ケアを徹底する。
残存機能の活用と自立支援
- ADLへのアプローチ
- できるだけ健側(麻痺していない側)を活用できるよう促す。
- 更衣は「患側から着て、健側から脱ぐ(脱健着患)」が基本。
- 食事の配膳位置は、健側に置くなど工夫する。
- 自助具や福祉用具の活用をOTと連携して検討し、使い方をサポートする。
- 精神的・心理的サポート
- 思うように体が動かせないことによる、患者の怒り、不安、抑うつなどの感情を受け止める。
- 傾聴の姿勢を大切にし、信頼関係を築く。
- リハビリなどでできたこと、小さな変化や進歩を認め、言葉で伝えることで、意欲を引き出す。
- 患者のセルフケアへの参加を促し、自己効力感を高められるよう支援する。
- 退院支援
- 退院後の生活を見据え、介護サービスの導入や家屋改修について、早期から医療ソーシャルワーカー(MSW)やケアマネジャーと連携する。
- 家族に対し、介助方法やリスク管理について指導する。