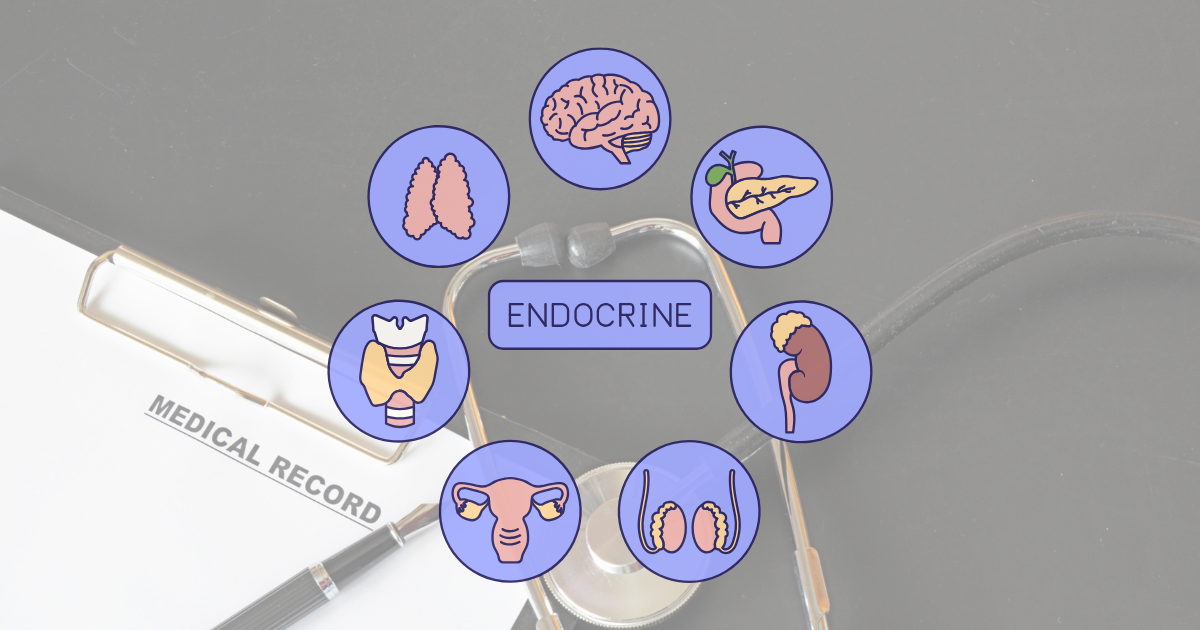Ⅰ型糖尿病の病態から看護のポイントまで徹底解説
 あずかん
あずかんⅠ型糖尿病は、子どもや若年層に多く発症しますが、成人や高齢者でも発症することがある自己免疫疾患です。患者さんは生涯にわたるインスリン補充が必要であり、看護師には専門的な知識に基づいたケアと、患者さんの自己管理を支えるための継続的なサポートが求められます。
この記事では、Ⅰ型糖尿病の患者さんを深く理解し、質の高い看護を実践するために必要な知識を、病態生理から具体的な看護のポイントまで詳しく解説します。
なぜインスリンが出なくなるのか
Ⅰ型糖尿病の核心は、膵臓のβ細胞が破壊されることによるインスリンの絶対的欠乏です。
通常、食事から摂取したブドウ糖は血液中に入り、血糖値が上昇します。これを感知した膵臓のランゲルハンス島にあるβ細胞からインスリンが分泌され、インスリンが血液中のブドウ糖を筋肉や脂肪細胞に取り込ませることで血糖値を下げ、エネルギー源として利用させます。
しかし、Ⅰ型糖尿病では、自己免疫反応によって免疫系がβ細胞を異物と誤認し、攻撃・破壊してしまいます。その結果、インスリンをほとんど、あるいは全く分泌できなくなり、ブドウ糖が細胞内に取り込まれず、血糖値が異常に高い状態(高血糖)が続きます。
インスリンが作用しないため、身体はエネルギー源として脂肪を分解し始めます。この過程でケトン体という酸性の物質が産生され、血液中に蓄積します。これが進行すると、糖尿病ケトアシドーシス(DKA)という生命を脅かす危険な状態に陥ります。
何が自己免疫反応を引き起こすのか
Ⅰ型糖尿病の直接的な原因は、前述の通り「自己免疫による膵β細胞の破壊」です。しかし、なぜ自己免疫反応が起きてしまうのか、その根本的なメカニズムは完全には解明されていません。
現在、最も有力な説は「遺伝的素因」と「環境因子」の相互作用です。
遺伝的素因
特定のHLA(ヒト白血球抗原)の型を持つ人は、Ⅰ型糖尿病を発症しやすいことが知られています。これは、免疫システムの働きに関わる遺伝子であり、特定の型を持つことで免疫の異常が起こりやすくなると考えられています。ただし、遺伝的素因を持つ人すべてが発症するわけではありません。
環境因子
ウイルス感染(コクサッキーウイルス、風疹ウイルスなど)、薬剤、食事、腸内細菌の変化などが引き金(トリガー)となり、遺伝的素因を持つ人において自己免疫反応が活性化されると考えられています。これらの因子が、β細胞に対する免疫攻撃のスイッチを入れてしまうのではないかと推測されています。
高血糖が引き起こす症状
インスリン欠乏による高血糖は、身体に様々なサインを引き起こします。特に急性発症期に見られる典型的な症状は以下の通りです。
- 口渇、多飲、多尿
血糖値が高くなると、腎臓は尿中にブドウ糖を排出しようとします(尿糖)。このとき、ブドウ糖と共に多くの水分が排出されるため、体は脱水状態になり、強い喉の渇き(口渇)を覚えます。その結果、水分を多く摂取する(多飲)ようになり、さらに尿量が増える(多尿)という悪循環に陥ります。 - 体重減少
インスリンが作用しないため、ブドウ糖をエネルギーとして利用できません。身体は代わりに筋肉や脂肪を分解してエネルギーを得ようとするため、食事を摂っていても急激に体重が減少します。 - 全身倦怠感
エネルギー不足により、疲れやすさやだるさを強く感じます。 - 意識障害(糖尿病ケトアシドーシス)
病状が進行し、ケトン体が増加して血液が酸性に傾くと(アシドーシス)、吐き気、嘔吐、腹痛、そして重篤な場合には昏睡状態(糖尿病性昏睡)に至ります。ケトアシドーシスは緊急治療を要する非常に危険な状態です。
治療・対症療法
Ⅰ型糖尿病の治療の根幹は、失われたインスリン分泌を体外から補充するインスリン療法です。これにより、血糖値を可能な限り正常範囲に近づけ、合併症の発症・進展を防ぎます。
- インスリン療法
- 頻回注射法(MDI): 1日に4〜5回、インスリンを自己注射する方法。食事の前に超速効型インスリンを、就寝前などに持効型溶解インスリンを注射するのが一般的です。
- 持続皮下インスリン注入療法(CSII、インスリンポンプ): 携帯型のポンプを用いて、皮下に留置したカニューレからインスリンを持続的に注入する治療法。より生理的なインスリン分泌パターンに近づけることが可能です。
- 血糖自己測定(SMBG)
- 患者自身が血糖測定器を用いて血糖値を測定し、その値に応じてインスリン投与量を調整します。血糖コントロールの基本となる重要な手技です。
- 持続血糖測定(CGM)
- 皮下にセンサーを装着し、グルコース値を24時間持続的に測定するシステムです。血糖値の変動パターンや無自覚性低血糖の発見に非常に有用です。
- 食事療法・運動療法
- Ⅱ型糖尿病とは異なり、食事や運動だけで血糖コントロールはできません。しかし、インスリンの効果を安定させ、良好なコントロールを維持するために、規則正しい食生活と適度な運動は重要です。
看護のポイント
- 急性期・診断初期の看護
- バイタルサインのモニタリングと全身管理: 特にケトアシドーシスを伴う場合は、救命が最優先です。医師の指示のもと、迅速な輸液、インスリン投与を行い、意識レベル、循環動態、電解質バランスなどを厳密にモニタリングします。
- 精神的サポート: ある日突然、生涯続く病気を告知された患者とその家族は、大きな衝撃と不安を抱えています。その心理的動揺に寄り添い、思いを表出できるような関わりや、正確な情報提供を通じて不安の軽減を図ることが重要です。
- 自己管理(セルフマネジメント)の教育と支援
- インスリン自己注射・血糖自己測定(SMBG)の手技指導: 患者が正確かつ安全に手技を習得できるよう、個別性を考慮して丁寧に指導します。手技の評価と再教育を継続的に行います。
- 低血糖・高血糖の対応指導: 低血糖・高血糖の症状、原因、対処法について、患者が理解し、実践できるよう具体的に指導します。特に低血糖は生命に危険を及ぼす可能性があるため、確実な対応(補食、ブドウ糖の携帯など)ができるように支援します。
- シックデイの対応: 発熱、嘔吐、下痢など、他の病気にかかった際の対応(シックデイルール)を指導します。インスリンの中断は絶対にしないこと、こまめな血糖測定と水分補給、医療機関への連絡のタイミングなどを具体的に伝えます。
- ライフステージに応じた継続的な支援
- 小児・思春期: 学校生活との両立(給食、体育、修学旅行など)、成長に伴うインスリン必要量の変化、心理的な葛藤(病気の受容、友人関係)など、発達段階に応じたきめ細やかなサポートが必要です。保護者との連携も欠かせません。
- 青年・成人期: 進学、就職、結婚、妊娠、出産など、ライフイベントに応じた血糖コントロールの調整や社会生活との両立を支援します。
- 高齢期: 視力低下や手指の巧緻性低下による自己管理能力の変化、合併症の管理、他の疾患との兼ね合いなどを考慮した支援が求められます。