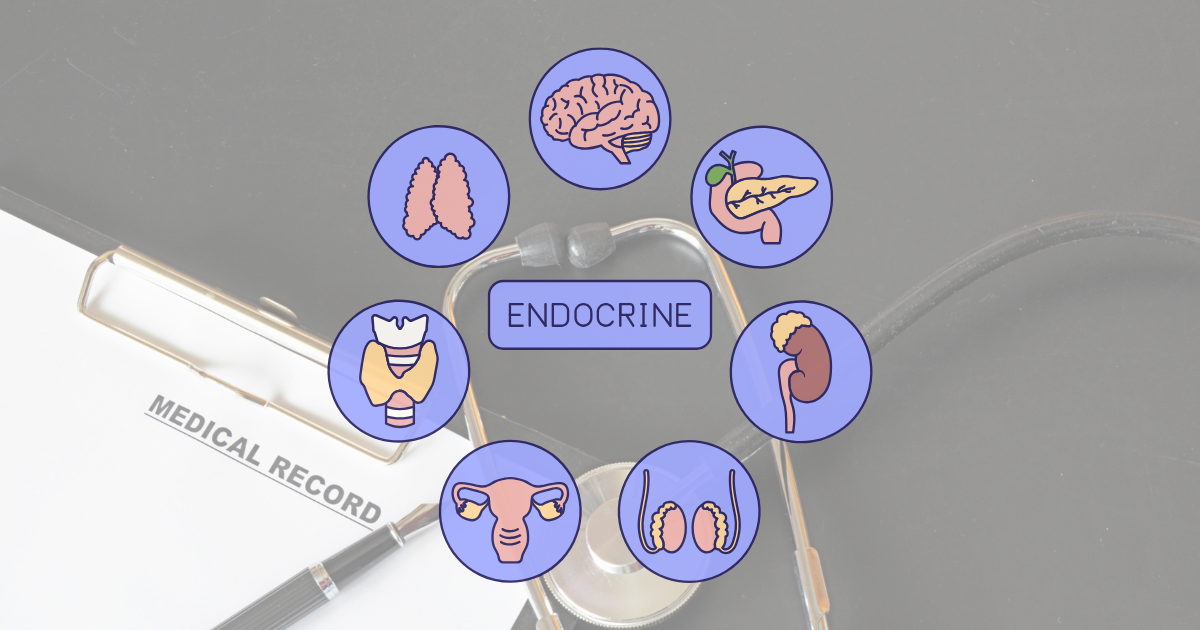甲状腺機能低下症について徹底解説
 あずかん
あずかん甲状腺機能低下症は、内分泌疾患の中でも比較的遭遇する機会の多い疾患です。しかし、その症状は非特異的でゆっくりと進行するため、「年のせい」「ただの疲れ」などと見過ごされがちです。この記事では、甲状腺機能低下症について、詳しく解説します。
甲状腺の働きとは
甲状腺ホルモンの働き
甲状腺から分泌される甲状腺ホルモン(主にサイロキシン T4 とトリヨードサイロニン T3)は、全身の細胞の新陳代謝を活性化させる役割を担っています。その働きは多岐にわたります。
基礎代謝の亢進: 全身の細胞の酸素消費量を増やし、熱を産生します。
心機能の促進: 心拍数や心収縮力を増加させます。
交感神経系の感受性向上: カテコールアミン(アドレナリンなど)への感受性を高めます。
成長・発達の促進: 特に胎児期や新生児期の中枢神経系の発達に不可欠です。
甲状腺機能低下症は、この甲状腺ホルモンの産生または作用が低下し、全身の代謝が抑制された状態を指します。
HPT軸によるフィードバック機構
甲状腺ホルモンの分泌は、脳の視床下部-下垂体-甲状腺(HPT軸)によって緻密にコントロールされています。
視床下部から甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(TRH)が分泌される。
TRHが下垂体を刺激し、甲状腺刺激ホルモン(TSH)が分泌される。
TSHが甲状腺を刺激し、甲状腺ホルモン(T4, T3)が分泌される。
血中の甲状腺ホルモン濃度が十分に高まると、視床下部と下垂体に作用し、TRHとTSHの分泌を抑制する(ネガティブフィードバック)。
甲状腺機能低下症の血液検査では、このフィードバック機構のどこに異常があるかを判断します。例えば、甲状腺自体の問題(原発性)では、甲状腺ホルモン(FT4, FT3)が低下し、それを補おうとしてTSHが高値になります。
甲状腺機能低下症の原因
甲状腺機能低下症は、原因となる部位によって大きく3つに分類されます。
原発性甲状腺機能低下症
甲状腺自体の原因で、機能が低下するケースです。全体の95%以上を占め、最も頻度が高いです。
- 橋本病(慢性甲状腺炎)
- 最も多い原因です。自己免疫疾患の一つで、自己抗体(抗TPO抗体、抗Tg抗体)が甲状腺組織を誤って攻撃し、慢性的な炎症を引き起こすことで、甲状腺細胞が徐々に破壊されていきます。
- 医原性
- 甲状腺全摘術・亜全摘術後: 甲状腺がんやバセドウ病の治療のために甲状腺を切除した場合。
- 放射性ヨウ素(アイソトープ)内用療法後: バセドウ病の治療で行われます。
- 頸部への放射線治療後: 悪性リンパ腫などで頸部に放射線照射を受けた場合。
- 薬剤性
- 抗不整脈薬のアミオダロン、免疫チェックポイント阻害薬、インターフェロンなどが原因となることがあります。
- 先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)
- 生まれつき甲状腺がない、または形成が不完全な状態です。早期発見・治療がなされないと、知的障害や発達障害につながるため、新生児マススクリーニングの対象となっています。
2. 中枢性甲状腺機能低下症(二次性・三次性)
下垂体(二次性)または視床下部(三次性)の異常により、TSHまたはTRHの分泌が低下し、結果として甲状腺ホルモンが分泌されなくなる状態です。
- 原因
- 下垂体腫瘍(最多)、シーハン症候群(分娩時の大量出血による下垂体壊死)、頭部外傷、放射線治療など。
- 特徴
- TSHが低値または基準範囲内であるにもかかわらず、FT4が低値を示します。副腎皮質や性腺など、他の下垂体ホルモン系の機能低下を合併していることが多いです。
甲状腺機能低下症の症状
甲状腺ホルモンは全身の代謝に関わるため、その症状は非常に多岐にわたります。ゆっくりと進行するため、患者自身が症状として自覚していないことも少なくありません。
| 分類 | 主な症状 |
|---|---|
| 全身症状 | 倦怠感 易疲労感 寒がり(低体温) 体重増加(代謝低下と水分貯留による) むくみ(特に非圧痕性浮腫=粘液水腫) 嗄声(声がかすれる) |
| 精神・神経症状 | 傾眠傾向 記憶力低下 集中力低下 無気力 抑うつ 認知機能低下 運動緩慢 |
| 皮膚・毛髪 | 皮膚の乾燥・蒼白 発汗減少 脱毛 眉毛の外側1/3が抜ける(ヘルトゲ徴候) |
| 循環器症状 | 徐脈 低血圧 心拡大 心嚢液貯留 |
| 消化器症状 | 食欲不振 便秘 イレウス(重症例) |
| 筋・骨格症状 | 筋力低下 こむら返り 関節痛 |
| 女性特有の症状 | 月経異常(過多月経、無月経など) 不妊 |
緊急性の高い病態:粘液水腫性昏睡
重度の甲状腺機能低下症を未治療のまま放置したり、感染症、手術、薬剤などを誘因として急激に悪化した場合に起こる、生命を脅かす緊急事態であり、死亡率が非常に高いため、迅速な対応が求められます。
主要な兆候
・意識障害(昏睡)
・著明な低体温(30℃以下になることも)
・呼吸抑制(CO2ナルコーシス)
・高度な徐脈、低血圧
治療・対症療法
治療の基本は、不足している甲状腺ホルモンを薬で補うホルモン補充療法です。
- 治療薬
- 合成T4製剤であるレボチロキシンナトリウム(商品名: チラージンS®など)が第一選択薬です。
- 通常、1日1回、朝食前に内服します。食事や他の薬剤(特に鉄剤やカルシウム製剤)との同時内服は吸収を妨げるため、時間を空ける必要があります。
- 投与量の調整
- 少量から開始し、血液検査(TSH, FT4)で効果を見ながら、4〜6週間かけて徐々に増量します。
- 特に高齢者や虚血性心疾患を持つ患者では、急激なホルモン補充が心臓に負担をかける(狭心症や心筋梗塞を誘発する)可能性があるため、「Start low, go slow(少量から始め、ゆっくり増やす)」が原則です。
- 治療期間
- 橋本病や甲状腺術後など、原因が不可逆的な場合は、原則として生涯にわたる内服が必要です。
- 粘液水腫性昏睡の治療
- 集中治療室(ICU)での管理が必要です。
- 甲状腺ホルモンの静脈内投与(日本では注射薬がないため経管投与)、副腎不全合併を考慮したステロイド投与、保温、呼吸管理、循環管理など集学的な治療が行われます。
看護のポイント
アセスメント
多彩な症状を見逃さず、重症化のサインを早期に発見することが重要です。
- バイタルサイン
- 徐脈、低血圧、低体温の傾向がないか定期的に評価します。特に低体温は重症度の指標となります。
- 全身状態の観察
- 皮膚・外見: 皮膚の乾燥、蒼白、浮腫(特に顔面、眼瞼、四肢の粘液水腫)、眉毛の状態を観察します。
- 意識レベル・精神状態: 傾眠傾向、会話の緩慢さ、記憶力低下、抑うつ気分などがないか、患者や家族とのコミュニケーションを通じてアセスメントします。認知症との鑑別も重要です。
- 身体症状のアセスメント
- 便秘: 排便の回数、性状、腹部膨満感の有無を確認します。
- 倦怠感・活動性: 日常生活動作がどの程度制限されているかを評価します。
- 検査データのモニタリング
- TSHとFT4の値の推移を把握し、治療効果や副作用(過量投与による機能亢進症状)の出現がないか確認します。
- 合併症の早期発見
- 意識レベルの低下、著しい低体温、呼吸抑制など、粘液水腫性昏睡を疑う兆候に細心の注意を払います。
看護介入
アセスメントに基づき、患者の苦痛を緩和し、安全を確保するためのケアを実践します。
- 環境調整(保温)
- 寒さを強く訴えるため、室温の調整、寝具(毛布など)の追加、温かい衣類の着用を促します。しかし電気毛布の使用は、低温やけどのリスクがあるため注意が必要です。
- 安楽の確保
- 皮膚ケア: 皮膚が乾燥し脆弱になっているため、保湿剤を塗布し、掻痒による皮膚損傷を防ぎます。
- 休息: 易疲労感が強いため、活動と休息のバランスを考慮したケアプランを立案し、十分な休息が取れる環境を整えます。
- 便秘への対応
- 水分摂取や食事内容(食物繊維)の工夫を促し、必要に応じて医師の指示のもと緩下剤を使用します。腹部マッサージも有効です。
- 安全確保
- 傾眠傾向や筋力低下による転倒・転落リスクを評価し、ベッド周囲の環境整備や歩行時の付き添いなど、必要な対策を講じます。
- 確実な服薬管理
- 治療の根幹であるホルモン補充療法が確実に行われるよう、内服の確認と管理を徹底します。特に高齢者や認知機能が低下している患者さんでは、家族の協力も得ながら支援します。
- 鉄剤や制酸薬など、吸収を阻害する薬剤との内服タイミングについて指導・管理します。
患者指導(セルフケア支援)
生涯にわたる自己管理が必要な疾患であるため、患者教育が極めて重要となります。
- 疾患の理解
- なぜこの病気が起こり、どのような症状が出るのかを、患者の理解度に合わせて分かりやすく説明します。治療によって症状が改善することを伝え、治療へのモチベーションを高めます。
- 服薬の重要性と継続
- 「症状が良くなったから」と自己判断で中断しないことの重要性を繰り返し伝えます。中断すると再び症状が悪化することを説明します。
- 生涯にわたる服薬が必要であることを、受容できるよう支援します。
- 副作用の知識
- 薬剤の過量投与によって、動悸、発汗、手の震え、体重減少といった甲状腺機能亢進症の症状が出現する可能性があることを伝えます。そのような症状が現れた場合は、すぐに医師や看護師に相談するよう指導します。
- 定期受診の必要性
- 定期的に血液検査を行い、薬の量を調整する必要があることを説明し、受診継続を促します。
- 日常生活での注意点
- バランスの取れた食事や適度な運動が推奨される一方、ヨウ素(昆布など)の過剰摂取は甲状腺機能に影響を与える可能性があるため、極端な摂取は避けるよう伝えます(ただし、通常の食事に含まれる量は問題ありません)。