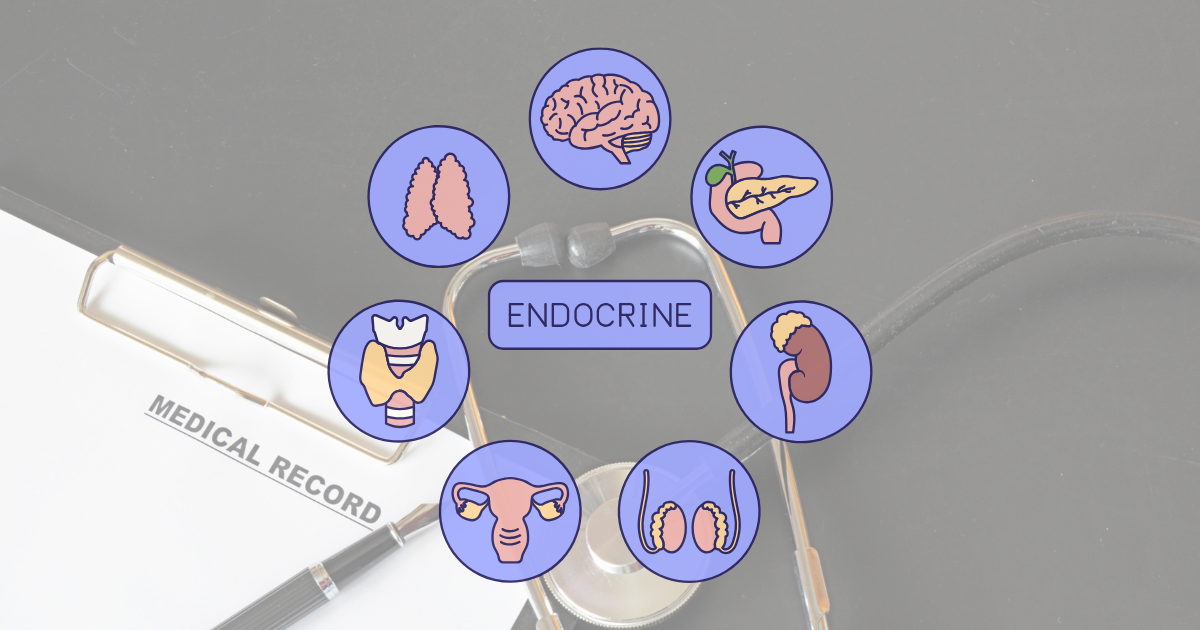副甲状腺機能低下症について徹底解説
甲状腺機能低下症との違い
「副甲状腺」と「甲状腺」は名前が似ており、首のあたりに存在する点も共通していますが、全く異なる働きを持つ内分泌器官です。それぞれの機能低下症は、現れる症状や治療法が大きく異なります。
| 項目 | 副甲状腺機能低下症 | 甲状腺機能低下症 |
|---|---|---|
| 主な役割 | カルシウム(Ca)・リン(P)濃度の調節 | 全身の代謝を促進するホルモンの分泌 |
| 分泌ホルモン | パラトルモン(PTH) | 甲状腺ホルモン |
| 主な症状 | 低カルシウム血症によるテタニー症状(しびれ、けいれん) | 代謝低下による全身倦怠感、むくみ、寒がり、体重増加など |
| 主な治療 | 活性型ビタミンD3製剤、カルシウム製剤の補充 | 甲状腺ホルモン製剤の補充 |
このように、副甲状腺はカルシウム代謝、甲状腺は全身の代謝と、全く別の役割を担っていることをまずは理解しましょう。
なぜテタニーが起こるのか
副甲状腺機能低下症は、副甲状腺から分泌されるパラトルモン(PTH)の作用不足により、血液中のカルシウム濃度が低下し(低カルシウム血症)、リン濃度が上昇する(高リン血症)病態です。
PTHには主に以下の3つの働きがあります。
骨吸収の促進:骨を溶かして、カルシウムとリンを血液中に放出させる。
腎臓でのカルシウム再吸収促進:尿として排泄されるカルシウムを体内に引き戻す。
腎臓でのビタミンD活性化:ビタミンDを活性型ビタミンDに変換し、腸管からのカルシウム吸収を促進する。
PTHが不足するとこれらの作用がすべて滞り、結果として低カルシウム血症と高リン血症をきたします。
【なぜ低カルシウム血症でテタニーが起こるのか?】
カルシウムイオンは、神経や筋肉の興奮性を調整する重要な役割を持っています。血中のカルシウム濃度が低下すると、神経細胞の興奮性が異常に高まります。これにより、わずかな刺激でも筋肉が収縮してしまい、テタニーと呼ばれる特徴的なけいれんや、手足のしびれといった症状が出現します。
なぜPTHは不足するのか
原因は大きく分けて、副甲状腺そのものに問題がある場合と、それ以外の要因による場合に分けられます。
- 特発性(原因不明)
- 自己免疫の異常などにより、副甲状腺の機能が損なわれると考えられています。
- 続発性(他の疾患や治療が原因)
- 頸部手術後:甲状腺がんやバセドウ病などの手術の際に、副甲状腺が一緒に摘出されたり、血流が障害されたりすることが最も多い原因です。
- 放射線治療後:頸部への放射線照射により、副甲状腺の機能がダメージを受けることがあります。
- 先天性
- 生まれつき副甲状腺が欠損している、または形成不全である場合があります(DiGeorge症候群)。
- 偽性副甲状腺機能低下症
- PTHの分泌は正常ですが、標的となる臓器(腎臓や骨)の感受性が低下しているため、PTHがうまく作用できない状態です。
低カルシウム血症が引き起こすサイン
症状の重症度は、低カルシウム血症の程度や進行スピードによって異なります。
- 神経・筋症状(テタニー症状)
- 感覚異常:口唇周囲、指先のしびれ感・ピリピリ感(最も初期に出やすい症状)
- テタニー発作:強い筋肉のけいれん。
- 助産師の手:手の筋肉が硬直し、指が特徴的な形になる。
- 痙笑(けいしょう):顔面の筋肉がこわばり、引きつった笑いのような表情になる。
- 全身けいれんを起こすこともあります。
- 潜在性テタニーの誘発
- クボステック徴候:耳下腺部(顔面神経)を軽く叩くと、顔面筋がけいれんする。
- トルーソー徴候:上腕をマンシェットで加圧し、血流を止めると「助産師の手」が現れる。
- 精神症状
- 不安感、いらだち、抑うつ、記憶力低下
- 自律神経症状
- 発汗、腹痛、下痢
- 皮膚・毛髪
- 皮膚の乾燥、脱毛、爪がもろくなる
- その他
- 白内障:長期にわたる低カルシウム血症で発症リスクが高まる。
- 大脳基底核の石灰化:パーキンソン症状(ふるえ、動作緩慢など)の原因となることがある。
- QT延長:心電図異常。重篤な不整脈につながる可能性がある。
治療・対症療法
治療の基本は、不足しているカルシウムを補い、血中カルシウム濃度を正常範囲に維持することです。
- 薬物療法
- 活性型ビタミンD3製剤:腸管からのカルシウム吸収を促進し、血中カルシウム値を上昇させる中心的な治療薬です。(例:アルファカルシドール、カルシトリオール)
- カルシウム製剤:食事からのカルシウム摂取が不十分な場合に併用します。(例:乳酸カルシウム、炭酸カルシウム)
- 急性期・テタニー発作時の対応
- グルコン酸カルシウムの静脈注射:血中カルシウム濃度を迅速に補正するために行います。血管外漏出による組織壊死のリスクがあるため、確実な静脈路の確保と慎重な投与が不可欠です。
- 食事療法
- 高カルシウム食:乳製品、小魚、緑黄色野菜などを積極的に摂取します。
- 低リン食:高リン血症がある場合は、リンを多く含む食品(加工食品、インスタント食品、一部の乳製品)の摂取を控えるよう指導します。
看護のポイント
副甲状腺機能低下症の患者さんへの看護では、症状のモニタリングと、安全な療養生活を送るための支援が重要になります。
- 低カルシウム血症症状(テタニー)の観察
- 初期症状の確認:患者からの「手足がしびれる」「口の周りがピリピリする」といった訴えを見逃さないことが最も重要です。
- バイタルサインの測定:特にQT延長のリスクがあるため、心電図モニターの監視や定期的な12誘導心電図の確認が重要です。
- 誘発徴候の確認:クボステック徴候やトルーソー徴候の有無を確認し、潜在的なテタニーのリスクをアセスメントします。
- 安全確保と環境調整
- テタニー発作やけいれんによる転倒・外傷を予防するため、ベッドサイドの環境を整備します。
- 緊急時に備え、救急カートや気道確保の物品、カルシウム製剤の静注準備をすぐに行えるようにしておきます。
- 確実な服薬管理と教育
- 治療は生涯にわたることが多いため、患者自身が病気と治療の必要性を理解し、服薬を継続できるよう支援します。
- 薬の飲み忘れは、容易に低カルシウム血症を引き起こすため、アドヒアランスを高めるための工夫(お薬カレンダーなど)を検討します。
- 低カルシウム血症の初期症状を患者自身が理解し、症状出現時にすぐ報告・相談できるよう指導します。
- 食事指導
- 管理栄養士と連携し、患者の食生活に合わせた具体的な高カルシウム・低リン食のメニューを提案します。
- 食品のリン含有量など、日常生活で実践しやすい情報提供が求められます。
- 精神的サポート
- 慢性的な経過や症状への不安、抑うつ傾向など、患者の精神的な側面に配慮した関わりが大切です。傾聴を通じて、不安の表出を促し、精神的な安定を図ります。