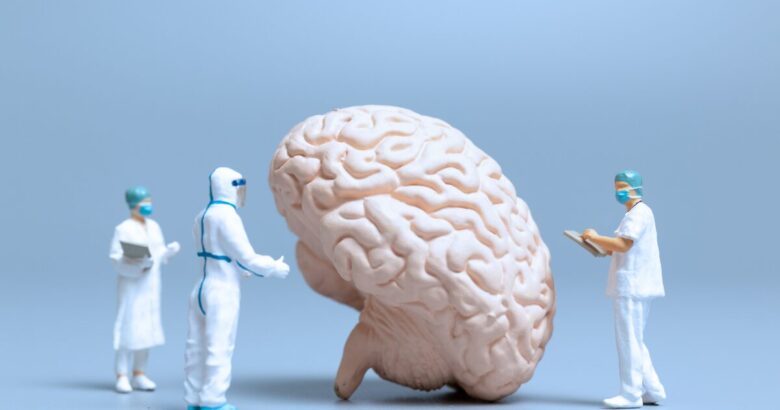レビー小体型認知症(DLB)の病態から看護のポイントまで徹底解説
 あずかん
あずかんレビー小体型認知症(DLB)は、アルツハイマー型認知症に次いで2番目に多い変性性認知症です。しかし、その症状の多様性から診断が難しく、現場の看護師には深い理解が求められます。
この記事では、レビー小体型認知症の患者さんをケアするために必要な知識を、病態生理から具体的な看護のポイントまで、分かりやすく解説します。
レビー小体型認知症とは
レビー小体型認知症は、脳の神経細胞内に「α-シヌクレイン」というタンパク質が異常に凝集して形成される「レビー小体」が出現することを特徴とします。このレビー小体が、大脳皮質や脳幹に広範囲にわたって蓄積することで、神経細胞が減少し、脳の機能が障害されます。
特に、ドパミンを産生する脳幹の黒質や、アセチルコリンを産生するマイネルト基底核などの神経細胞が障害されやすいことが知られており、これにより、後述する特徴的な症状(パーキンソン症状、認知機能障害など)が引き起こされます。
レビー小体型認知症の原因
レビー小体型認知症の根本的な原因は、まだ完全には解明されていません。しかし、主にα-シヌクレインというタンパク質の異常が関与していると考えられています。
正常な状態では、α-シヌクレインは脳内で重要な役割を果たしていますが、何らかの理由でその構造が変化し、凝集しやすくなることでレビー小体が形成されます。遺伝的要因や環境要因が複雑に関与していると考えられていますが、多くの場合は孤発性(遺伝性ではない)です。
レビー小体型認知症の症状
レビー小体型認知症の症状は非常に多彩ですが、以下の4つが中核的な特徴とされています。
- 変動する認知機能
- 日や時間帯によって、注意・覚醒レベルが大きく変動します。しっかりしている時と、ぼんやりしている時の差が激しいのが特徴です。
- 会話が噛み合ったかと思えば、急に無反応になったり、眠っているように見えたりすることがあります。
- 具体的な幻視
- 「そこに人がいる」「虫がたくさんいる」など、非常にリアルで具体的な幻視を繰り返し訴えます。
- 幻視の内容を信じ込んでいるため、否定せずに受け止める姿勢が重要です。
- パーキンソン症状
- 動作が遅くなる(無動)、筋肉がこわばる(固縮)、手が震える(振戦)、バランスがとりにくく転びやすくなる(姿勢反射障害)といった、パーキンソン病に似た運動症状が現れます。
- これにより、日常生活動作(ADL)が大きく低下します。
- レム睡眠行動障害
- 睡眠中に、夢の内容に合わせて大声で叫んだり、手足を激しく動かしたりする症状です。
- 通常、レム睡眠中は筋肉の緊張が抑制されますが、その機能が障害されることで起こります。本人に自覚がないことが多いです。
これらの他にも、自律神経症状(便秘、頻尿、起立性低血圧など)やうつ症状、嗅覚の低下なども見られます。
治療・対症療法
現時点では、レビー小体型認知症を根本的に治す治療法はありません。そのため、薬物療法と非薬物療法を組み合わせ、症状を緩和し、生活の質(QOL)を維持することが治療の目標となります。
- 薬物療法
- 認知機能障害に対して:コリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジルなど)が有効な場合があります。
- パーキンソン症状に対して:レボドパ製剤などが使用されますが、幻視などの精神症状を悪化させる可能性があり、慎重な投与が必要です。
- 幻視や妄想に対して:非定型抗精神病薬が使用されることがありますが、副作用(特にパーキンソン症状の悪化)のリスクが高いため、ごく少量から開始します(薬剤過敏性)。
- 非薬物療法
- リハビリテーション:パーキンソン症状によるADL低下を防ぐため、理学療法や作業療法が重要です。
- 環境調整:幻視を誘発しないように部屋を明るくしたり、転倒予防のために手すりを設置したりするなどの工夫が必要です。
- 心理的サポート:不安や恐怖を傾聴し、安心感を与える関わりが大切です。
看護のポイント
- 認知機能の変動への対応
- 患者の状態が良い時に、コミュニケーションをとったり、ケアを集中して行ったりするなどの工夫をしましょう。
- 状態が悪い時は無理強いせず、休息を促します。ご家族にもこの変動について説明し、理解を求めましょう。
- 幻視への対応
- 幻視を頭ごなしに否定せず、「そうですか、〜が見えるのですね」とまずは受け止め、共感的な態度で接します。
- 恐怖や不安を訴える場合は、「大丈夫ですよ」と安心できるような声かけをし、そばに寄り添います。
- 部屋の照明を明るくしたり、紛らわしい物を片付けたりする環境調整も有効です。
- 転倒・転落の予防
- パーキンソン症状や起立性低血圧により、転倒リスクが非常に高いです。
- ベッド周りの環境整備(手すり、低床ベッド)、滑りにくい履物、歩行状態のアセスメントを徹底しましょう。
- 離床センサーの活用も検討します。
- 薬剤過敏性への注意
- 特に抗精神病薬に対して過敏な反応を示すことがあります。薬剤の開始・増量後は、パーキンソン症状の悪化や傾眠、嚥下機能の低下などの副作用を注意深く観察しましょう。
- ご家族への支援
- 症状の変動や幻視など、理解しがたい症状に戸惑い、介護負担を感じているご家族は少なくありません。
- 病気について分かりやすく説明し、ご家族の気持ちを傾聴・共感することで、心理的負担を軽減し、協力関係を築くことが大切です。