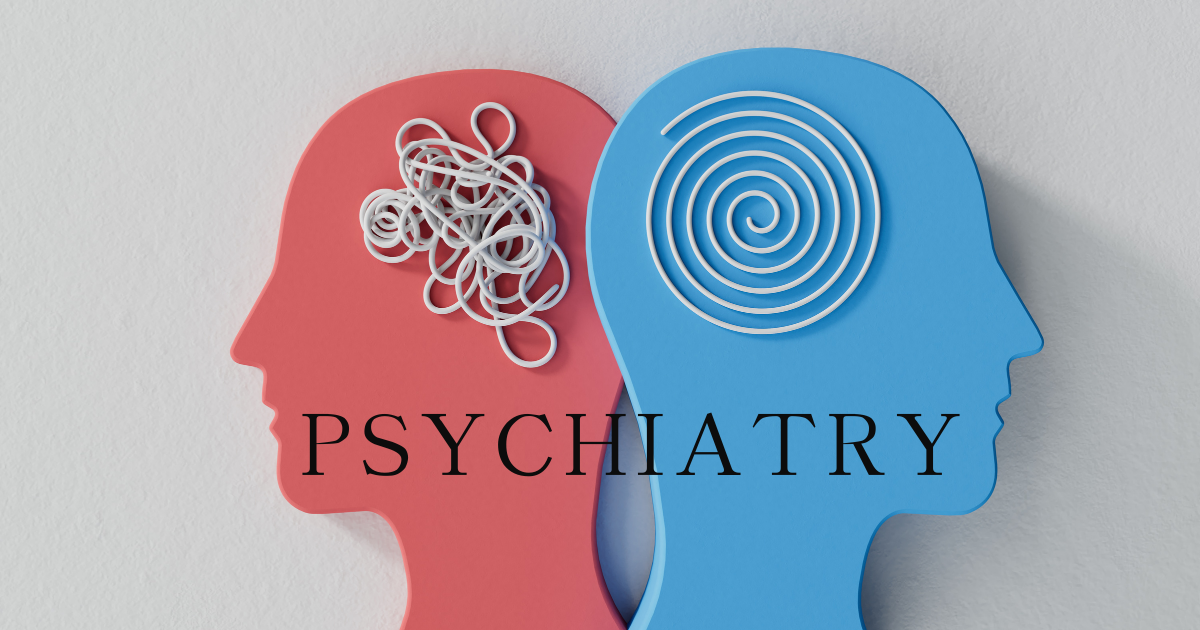うつ病の病態生理と看護のポイントを徹底解説
 あずかん
あずかん看護師として、私たちは日々さまざまな疾患を持つ患者さんと接します。その中でも、心の病である「うつ病」は、身体的な疾患とは異なるアプローチが求められる、非常に奥深い領域ですが、どのように関われば良いか戸惑うことも多い領域でもあります。
この記事では、うつ病の基本的な知識から実践的な看護のポイントまで、分かりやすく解説していきます。
脳の中で何が起きているのか
うつ病は「気分の落ち込み」や「意欲の低下」といった精神的な症状が注目されがちですが、その背景には脳の機能的な変化があると考えられています。単なる「気の持ちよう」ではないことを理解することが、適切なケアの第一歩です。現在のところ、うつ病の病態生理は完全には解明されていませんが、主に以下の3つの仮説が有力とされています。
モノアミン仮説
脳内の神経伝達物質であるセロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンなどの「モノアミン」の量が減少、または機能が低下することで、情報伝達がスムーズに行かなくなり、うつ症状が引き起こされるという説です。多くの抗うつ薬は、このモノアミンの脳内濃度を高める作用を持っています。
神経可塑性の異常
脳は経験や学習によって常に変化する能力(神経可塑性)を持っています。しかし、慢性的なストレスは、記憶や情動に関わる「海馬」などの脳領域を萎縮させ、神経細胞の新生を妨げることが分かってきました。これにより、気分調節や認知機能に異常が生じると考えられています。
HPA系の機能亢進
HPA系(視床下部-下垂体-副腎系)は、ストレス反応を制御する重要なシステムです。強いストレスにさらされ続けると、このHPA系の活動が過剰になり、ストレスホルモンである「コルチゾール」が過剰に分泌されます。高濃度のコルチゾールは、海馬の神経細胞を傷つけ、うつ病の発症に関与すると考えられています。
これらの要因が複雑に絡み合い、うつ病の多様な症状を引き起こしていると理解されています。
うつ病はなぜ発症するのか
うつ病の発症は、単一の原因で説明できるものではありません。その人のもつ生物学的要因、心理社会的要因、環境要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
生物学的要因
遺伝的要因
家族にうつ病の人がいる場合、発症リスクがやや高まることが知られていますが、遺伝だけで決まるわけではありません。
身体疾患
甲状腺機能低下症、脳血管障害、がん、慢性的な痛みなども、うつ病の引き金となることがあります。
心理社会的要因
性格傾向
真面目、責任感が強い、完璧主義、他者への配慮が深いといった性格の人は、ストレスを溜め込みやすい傾向があると言われています。
認知の歪み
物事を悲観的に捉えたり、自分を責めたりする思考パターンが、うつ病の維持・悪化に関与することがあります。
環境要因
ストレスの多い出来事
身近な人との死別、離婚、失業、経済的な問題など、つらい出来事が発症のきっかけになることがあります。
継続的なストレス
過重労働、人間関係のトラブル、介護疲れなど、長期間にわたるストレスも大きな原因となります。
ライフイベント
昇進、結婚、出産など、喜ばしい出来事であっても、環境の大きな変化がストレスとなり、発症のきっかけになることもあります。
これらの要因が重なったとき、誰にでもうつ病を発症する可能性があります。
うつ病の主な症状
うつ病の症状は、精神的なものから身体的なものまで多岐にわたります。これらのサインに早期に気づき、アセスメントに活かすことが重要です。
- 精神症状
- 抑うつ気分: 気分が沈み込み、何をしても晴れない。悲しい、空しい、絶望的な気持ちになる。
- 興味・喜びの喪失: これまで楽しめていた活動(趣味、テレビなど)に全く興味が湧かなくなり、喜びを感じられなくなる。
- 思考力・集中力の低下: 注意が散漫になり、仕事や家事に集中できない。決断ができない。本の内容が頭に入らない。
- 意欲の低下・億劫さ: 何かをするのがひどく億劫に感じ、気力が湧かない。入浴や着替えさえ面倒になる。
- 自責感・無価値感: 「自分はダメな人間だ」「周りに迷惑をかけている」と過剰に自分を責める。
- 希死念慮: 「生きていても仕方がない」「消えてなくなりたい」といった考えが浮かぶ。
- 身体症状
- 睡眠障害: 寝つきが悪い(入眠困難)、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)、朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)。逆に、過度に眠りすぎてしまう過眠もみられます。
- 食欲の変化: 食欲が全くなくなる(食欲不振)、または逆に甘いものや炭水化物を過剰に食べてしまう(過食)。それに伴う体重の減少または増加。
- 疲労感・倦怠感: 十分に休んでも疲れが取れず、常に身体がだるい、重いと感じる。
- 身体の痛み: 頭痛、肩こり、腰痛、胃の不快感など、特定の原因が見当たらない身体の痛み(不定愁訴)。
- その他: 動悸、めまい、口の渇き、性欲の減退など。
これらの症状が2週間以上、ほぼ毎日続く場合にうつ病が疑われます。特に「抑うつ気分」と「興味・喜びの喪失」のどちらか一方は、診断において必須の症状です。
治療・対症療法
うつ病の治療は、「休養」「薬物療法」「精神療法」の3つを柱として進められます。患者の状態に合わせて、これらの治療を組み合わせて行います。
- 1. 十分な休養
うつ病は「心のエネルギーが枯渇した状態」です。まずは心と身体をしっかりと休ませ、エネルギーを回復させることが最も重要です。必要に応じて、休職や休学の診断書が発行されることもあります。看護師は、患者が罪悪感なく休めるよう環境を整え、休養の重要性を伝える役割を担います。 - 2. 薬物療法
- 抗うつ薬: 主にSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)やSNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)が第一選択薬として用いられます。これらの薬は、脳内の神経伝達物質のバランスを整えることで、症状の改善を図ります。効果が表れるまでに2~4週間かかること、副作用(吐き気、眠気など)、自己判断で中断しないことなどを丁寧に説明する必要があります。
- その他: 不安が強い場合には抗不安薬、不眠が強い場合には睡眠導入剤が併用されることもあります。
- 3. 精神療法(心理療法)
薬物療法と並行して行われ、再発予防にも効果的です。- 認知行動療法 (CBT): 物事の受け取り方(認知)や行動パターンに働きかけ、より現実的でバランスの取れた考え方ができるようにサポートする治療法です。悲観的な思考の癖を修正していきます。
- 対人関係療法 (IPT): 対人関係のストレスに着目し、コミュニケーションのパターンを見直すことで、現在の問題解決をサポートする治療法です。
- 支持的精神療法: 医師やカウンセラーが患者の話に耳を傾け、共感的に関わることで、患者を心理的に支えます。
- 4. その他の治療法
- 修正型電気けいれん療法 (m-ECT): 重症で、薬物療法への反応が乏しい場合や、希死念慮が非常に強く緊急性が高い場合などに行われる治療法です。全身麻酔下で頭部に微弱な電流を流し、脳にてんかん発作を誘発することで、症状の急速な改善を図ります。
- 反復性経頭蓋磁気刺激法 (rTMS): 磁気を用いて脳の特定部位を刺激し、機能の回復を促す治療法です。副作用が比較的少なく、m-ECTよりは身体的負担が少ないとされています。
看護のポイント
うつ病患者への看護は、急性期、回復期、維持期(再発予防期)といった病状のフェーズによって異なります。ここでは、共通して重要となる関わり方の基本と、各時期のポイントを解説します。
関わり方の基本
- 受容と傾聴
患者のつらい気持ちや訴えを否定せず、「つらいのですね」とそのまま受け止め、話を真摯に聴く姿勢が基本です。安易な励まし(「頑張って」など)は、患者をさらに追い詰めてしまうため避けましょう。 - 安心できる環境の提供
患者が安心して過ごせるよう、静かで刺激の少ない環境を整えます。また、看護師自身が穏やかで落ち着いた態度で接することが、患者の安心感につながります。 - 自殺企図のリスクアセスメント
希死念慮はうつ病の重要な症状です。「死にたい気持ちはありますか?」と直接的に、かつ共感的に尋ねることが不可欠です。リスクが高いと判断した場合は、医師に報告し、見守りの強化や環境調整(危険物の除去など)を行います。
病期ごとの看護ポイント
急性期(症状が最も重い時期)
目標: 安全の確保と基本的なニーズの充足
具体的なケア
安全確保: 希死念慮のアセスメントと自殺予防策を最優先します。
休養の促進: 活動を無理強いせず、ゆっくりと休めるように関わります。
セルフケア援助: 入浴、食事、排泄など、患者の状態に合わせて必要な援助を行います。自分でできることは尊重し、過剰な介入は避けます。
服薬管理: 副作用の観察と、確実に服薬できるようサポートします。
回復期(症状が少しずつ改善する時期)
目標: 活動性の向上と自信の回復
具体的なケア
活動の促し: 患者の意欲に合わせて、散歩や簡単なレクリエーションなど、負担の少ない活動を少しずつ提案します。
自己肯定感のサポート: できたこと(「散歩に行けた」「食事を完食できた」など)を具体的にフィードバックし、自信を取り戻せるように支援します。
意思決定の支援: 簡単な選択(「お茶と水、どちらがいいですか?」など)から促し、徐々に自己決定の機会を増やしていきます。
心理教育: 疾患や薬について説明し、患者自身が病気を理解し、治療に主体的に取り組めるよう支援します。
維持期・再発予防期(社会復帰を目指す時期)
目標: 再発予防とセルフマネジメント能力の向上
具体的なケア
再発のサインの確認: 気分の変動や睡眠状態など、再発の初期サインを患者と一緒に確認し、早期対処できるようにします。
ストレスコーピング: ストレスへの対処法(相談する、リラックス法を試すなど)を一緒に考え、身につけられるよう支援します。
社会資源の活用支援: デイケア、作業所、地域の相談窓口など、利用できる社会資源の情報を提供し、必要に応じて関係機関と連携します。
家族への支援: 家族もまた、患者を支える上で重要な存在です。家族の悩みを聞き、疾患への理解を深め、適切な関わり方ができるようサポートします。