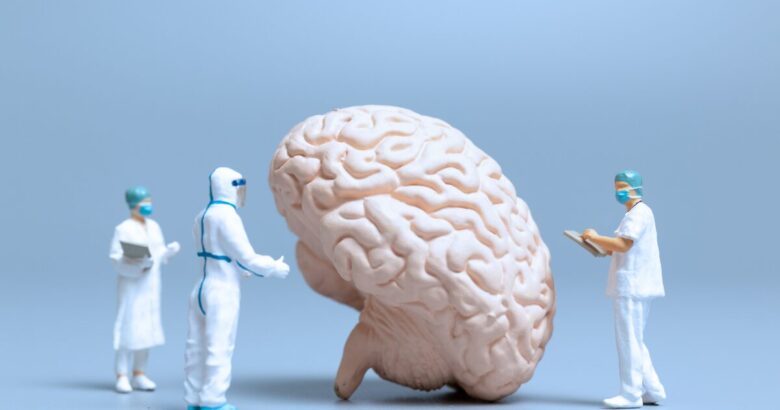解離性脳動脈瘤の病態から看護のポイントまで徹底解説
 あずかん
あずかん解離性脳動脈瘤は、くも膜下出血や脳梗塞の原因となる重篤な疾患です。しかし、その病態は一般的な嚢状動脈瘤とは異なり、少し複雑に感じるかもしれません。
この記事では、解離性脳動脈瘤の基礎知識から具体的な看護のポイントまで、徹底解説します。
解離性脳動脈瘤について
解離性脳動脈瘤は、脳の動脈壁が裂けることによって発生します。
私たちの血管は、内側から内膜、中膜、外膜の3層構造になっています。何らかの原因で内膜に亀裂が入ると、そこから血液が血管壁の内部(主に中膜)に流れ込み、血管壁が内外の2層に引き剥がされてしまいます。この状態を「解離」と呼びます。解離が起こると、2つの大きな問題が生じます。
血管の狭窄・閉塞
解離によってできた偽腔(血液が流れ込んだ空間)が、本来の血流が通る真腔を圧迫し、血流が悪化します。これにより、脳梗塞を引き起こすことがあります。
血管の破裂
解離によって血管壁が脆弱になり、外膜一枚で血液を支える状態になります。この状態が進行すると、血管が破裂し、くも膜下出血を引き起こす危険性が高まります。
特に、椎骨動脈や内頚動脈に好発することが知られています。
解離性脳動脈瘤の原因
解離性脳動脈瘤の明確な原因はまだ完全には解明されていませんが、以下の要因が関与していると考えられています。
血行力学的ストレス
高血圧や、急激な血圧変動が血管壁に物理的な負担をかけ、内膜の亀裂を誘発する可能性があります。
血管壁の脆弱性
先天的な血管の構造異常や、線維筋性異形成症などの基礎疾患がある場合、血管壁が弱くなり解離を起こしやすくなります。
軽微な外傷
首を急にひねる、カイロプラクティック、スポーツなどによる頭頸部への物理的な衝撃が、血管壁の損傷につながることがあります。
その他
感染症や血管炎なども、リスク因子として挙げられています。
必ずしも高血圧や動脈硬化が背景にあるわけではなく、若年層にも発症することが特徴です。
解離性脳動脈瘤の症状
解離性脳動脈瘤の症状は、解離が起きた場所や、それに伴う合併症(脳梗塞、くも膜下出血)によって大きく異なります。
くも膜下出血を発症した場合
突然の激しい頭痛:「バットで殴られたような」と表現されるほどの、これまでに経験したことのないような強い頭痛が特徴
悪心・嘔吐
意識障害
痙攣
脳梗塞を発症した場合
片麻痺(体の片側の手足の麻痺)
感覚障害
言語障害(ろれつが回らない、言葉が出ないなど)
めまい、ふらつき
上記以外(未破裂の場合)
後頭部から首にかけての痛み:椎骨動脈解離でよく見られる症状
ホルネル症候群(内頚動脈解離の場合):縮瞳、眼瞼下垂、顔面の発汗低下などがみられる
特徴的なのは、くも膜下出血や脳梗塞といった重篤な症状が出現する前に、前駆症状として後頭部痛や頸部痛がみられることがある点です。これらのサインを見逃さないことが、早期発見・早期治療において非常に重要です。
治療・対症療法
治療方針は、動脈瘤の部位、形状、症状(未破裂か、破裂しているか)、合併症の有無などを総合的に評価して決定されます。
保存的治療
主に未破裂で症状が安定している場合に選択されます。
- 血圧管理
降圧薬を用いて、血管壁への負担を軽減し、解離の拡大や破裂を防ぎます。収縮期血圧を120mmHg未満など、厳格なコントロールが求められます。 - 抗血小板療法・抗凝固療法
脳梗塞を合併している場合や、血栓形成による症状悪化を防ぐ目的で使用されます。アスピリンなどが代表的です。ただし、出血リスクを高めるため、破裂の危険性がある症例には慎重に投与されます。
外科的治療(血管内治療・開頭手術)
破裂した場合や、保存的治療で症状が進行する場合、将来的な破裂リスクが高いと判断された場合に選択されます。
- 血管内治療
カテーテルを用いて、解離した血管を内側から修復する方法です。- コイル塞栓術:解離腔や動脈瘤内にプラチナ製のコイルを詰めて、血流を遮断します。
- ステント留置術:金属のメッシュでできた筒(ステント)を血管内に留置し、真腔を確保し、偽腔への血流を遮断します。
- 開頭手術
頭蓋骨を開けて、直接動脈瘤を処置する方法です。- クリッピング術:動脈瘤の根元をクリップで挟み、血流を遮断します。
- ラッピング術:動脈瘤を補強材で包み込み、破裂を防ぎます。
- バイパス術:血流が遮断される領域に対して、別の血管をつなぎ、血流を確保します。
対症療法
出現している症状を和らげるための治療です。
- 鎮痛薬:頭痛や頸部痛に対して使用します。
- 制吐薬:悪心・嘔吐に対して使用します。
- 脳圧降下薬:くも膜下出血による脳浮腫や水頭症に対して使用します。
看護のポイント
血圧管理(再出血の予防と解離の拡大防止)
・医師の指示に基づいた目標血圧を厳守します。Aラインが挿入されている場合は、常に波形と数値を監視します。
・降圧薬が持続投与されている場合は、流量管理を徹底します。
・排便時の怒責、体位変換、ケア時の疼痛など、血圧を上昇させる要因をできるだけ排除します。必要に応じて鎮痛薬や緩下剤の使用を検討します。
・精神的な安静も重要です。病状や治療について分かりやすく説明し、不安の軽減に努めます。
症状の観察(再出血、脳梗塞、脳血管攣縮、水頭症などの合併症の早期発見)
・意識レベル:JCSやGCSを用いて、経時的に評価します。傾眠傾向や見当識障害など、わずかな変化も見逃さないようにします。
・神経学的所見:瞳孔径・対光反射、麻痺の有無・程度、感覚障害、言語障害などを注意深く観察します。
・頭痛:痛みの部位、程度(VASなど)、性質の変化を確認します。「痛みが急に強くなった」「痛む場所が変わった」などの訴えは、再出血や解離拡大のサインである可能性があります。
・髄膜刺激症状:項部硬直、ケルニッヒ徴候、ブルジンスキー徴候の有無を確認します。くも膜下出血の増悪を示唆します。
・尿量:尿崩症やSIADH(抗利尿ホルモン不適合分泌症候群)の合併にも注意し、尿量と水分出納バランスを監視します。
安静の保持(血圧変動を防ぎ、再出血リスクを低減する)
・絶対安静の指示がある場合は、食事、排泄、清拭など、全ての日常生活動作をベッド上で行います。
・患者自身が動いてしまうことのないよう、安静の必要性を丁寧に説明し、協力を得ます。
・ナースコールの位置を調整し、患者さんがいつでも助けを求められる環境を整えます。
精神的ケア(突然の発症による不安や恐怖を軽減する)
・患者やご家族の訴えを傾聴し、共感的な態度で関わります。
・治療や検査の目的、内容を理解度に合わせて説明し、見通しが持てるように援助します。
・ICU/HCUなどの特殊な環境では、昼夜のリズムが乱れやすいため、環境調整を行い、せん妄を予防します。