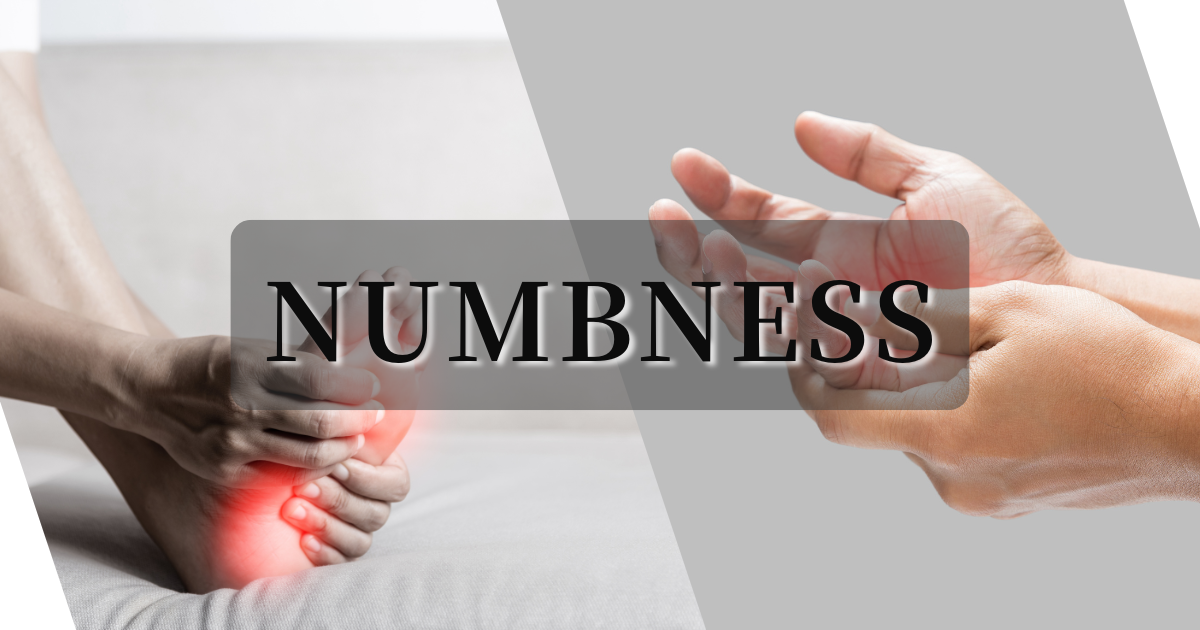四肢のしびれを徹底解説!原因から看護ケアまで
 あずかん
あずかん四肢のしびれは、臨床現場で頻繁に遭遇する症状の一つです。患者さんのQOLに大きく影響を与えるだけでなく、重大な疾患のサインである可能性もあります。この記事では、、四肢のしびれの病態生理から看護のポイントまでを詳しく解説していきます。
目次
四肢のしびれとは
しびれ(感覚鈍麻・異常感覚)は、末梢神経または中枢神経(脊髄・脳)のいずれかの経路に障害が起こることで発生します。私たちの感覚は、皮膚などにある受容器が刺激をキャッチし、その情報が電気信号として末梢神経を通り、脊髄を経由して脳に伝わることで認識されまが、この「感覚の伝導路」のどこかに問題が生じると、しびれとして現れるのです。
障害のメカニズムは主に3つに分けられます。
- 圧迫(機械的障害)
神経が骨、腫瘍、椎間板ヘルニアなどによって物理的に圧迫されると、神経内の血流が阻害され、酸素や栄養が不足します。これにより神経細胞の機能が低下し、正常な情報伝達ができなくなります。正座をした後の足のしびれは、この典型的な例です。 - 炎症・損傷
事故による外傷や、帯状疱疹ウイルスのように神経自体に炎症が起こると、神経細胞が直接ダメージを受け、異常な電気信号が発生したり、信号が途絶えたりします。 - 血流障害・代謝異常
糖尿病や動脈硬化により、神経に栄養を送る細い血管の血流が悪化すると、神経細胞は慢性的な栄養不足に陥り、機能が低下します(虚血性障害)。また、ビタミンB群の欠乏やアルコールによる代謝異常も、神経の正常な働きを妨げる原因となります。
しびれの原因
しびれの原因は極めて多岐にわたりますが、障害される部位によって「末梢神経性」と「中枢神経性」に大別することが重要です。
末梢神経性の原因
| カテゴリ | 具体的な疾患・状態 | 特徴 |
|---|---|---|
| 圧迫によるもの | 手根管症候群 肘部管症候群 椎間板ヘルニア 脊柱管狭窄症 胸郭出口症候群 | 特定の神経がトンネルや骨、腫瘍などによって物理的に圧迫される。特定の姿勢で増悪することが多い。 |
| 代謝・内分泌性 | 糖尿病性神経障害 ビタミンB群欠乏症 甲状腺機能低下症 腎不全(尿毒症性ニューロパチー) | 高血糖や代謝産物の蓄積、栄養不足が神経細胞にダメージを与える。特に糖尿病は多発神経障害の最多の原因。 |
| 血管性 | 閉塞性動脈硬化症(ASO) 血管炎 | 動脈硬化や血管の炎症により、神経への血流が阻害され、虚血状態に陥る。 |
| 感染症・炎症性 | ギラン・バレー症候群 帯状疱疹後神経痛 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP) | ウイルス感染などを引き金に、自己免疫反応が神経(特に髄鞘)を攻撃する。 |
| その他 | 薬剤性(抗がん剤、抗菌薬など) アルコール性 外傷による神経損傷 遺伝性(シャルコー・マリー・トゥース病) | 化学物質や物理的なダメージが直接神経を傷つける。 |
中枢神経性の原因
| 疾患 | 特徴 |
|---|---|
| 脳血管障害(脳梗塞・脳出血) | 突然発症し、多くは片側の顔面と手足にしびれ・麻痺が生じる。呂律障害、意識障害、視野障害などを伴うことがある。緊急対応が必要。 |
| 脳腫瘍 | 症状は数週間~数ヶ月かけてゆっくりと進行する。頭痛、けいれん、高次脳機能障害などを伴うことがある。 |
| 脊髄疾患 | 脊髄損傷、脊髄梗塞、脊髄腫瘍、多発性硬化症、頚椎症性脊髄症など。障害された高位以下の両側性にしびれや麻痺、膀胱直腸障害が生じることが多い。 |
しびれの症状による分類
単神経障害(単ニューロパチー)
1本の末梢神経が単独で障害される状態です。しびれや筋力低下は、その神経が支配する領域に限定して現れます。
- 原因: 主に圧迫や外傷。
- 代表例
- 手根管症候群: 手首で正中神経が圧迫。母指~薬指半分の掌側のしびれ。
- 肘部管症候群: 肘で尺骨神経が圧迫。小指と薬指半分のしびれ。
- 橈骨神経麻痺: 上腕部での圧迫。下垂手(手首が上がらない)が特徴。
多発神経障害(多発ニューロパチー)
多数の末梢神経が、全身で左右対称性に障害される状態です。
- 特徴
多くは「手袋靴下型」と呼ばれ、最も線維が長い足先や指先から症状が始まり、徐々に体幹に向かって上行します。 - 代表例
糖尿病性神経障害、アルコール性神経障害、ギラン・バレー症候群、薬剤性神経障害。
多発性単神経障害(多発単ニューロパチー)
異なる場所にある複数の末梢神経が、非対称的かつ非連続的に、時間差で障害されていく状態です。
- 特徴
例えば「右手の正中神経麻痺と、数週間後の左足の腓骨神経麻痺」のように、バラバラに症状が出現します。 - 代表例
血管炎(結節性多発動脈炎など)、膠原病(関節リウマチなど)、サルコイドーシス。
神経根症(ラディキュロパチー)
脊髄から分岐した直後の「神経根」が、椎間孔(骨のトンネル)で圧迫される状態です。
- 特徴
しびれや痛み(放散痛)が、障害された神経根に対応する皮膚領域**(デルマトーム)**に沿って、帯状に広がります。咳、くしゃみ、特定の頚部や体幹の動きで症状が増悪(誘発)されることがあります。 - 代表例
頚椎症性神経根症、腰椎椎間板ヘルニア。
治療・対症療法
治療は、原因疾患に対する原因療法と、しびれという症状自体を和らげる対症療法の2本柱で行われます。
1. 原因療法
- 圧迫の除去: 椎間板ヘルニアや手根管症候群などに対して、手術による除圧術が行われることがある。
- 原疾患の管理: 糖尿病の血糖コントロール、ビタミン欠乏の補充、甲状腺機能の正常化など。
- 免疫抑制・調節: ギラン・バレー症候群やCIDP、血管炎に対して、ステロイド療法、免疫グロブリン大量静注療法、血漿交換療法などが行われる。
- 薬剤の中止・変更: 薬剤性が原因の場合、可能であれば原因薬剤を中止または変更する。
2. 対症療法(薬物療法)
しびれ、特に陽性症状である痛み(神経障害性疼痛)に対しては、通常の鎮痛薬(NSAIDsなど)は効果が薄いことが多く、以下の薬剤が用いられます。
- Ca²⁺チャネルα2δリガンド: プレガバリン(リリカ)、ミロガバリン(タリージェ)。過剰に興奮した神経を鎮静化させる。
- 抗うつ薬: デュロキセチン(サインバルタ)、アミトリプチリン。痛みを下行性に抑制する神経伝達物質(セロトニン、ノルアドレナリン)を増やす。
- その他: ビタミンB12製剤(メコバラミン)、オピオイド鎮痛薬(トラマドールなど)、漢方薬(牛車腎気丸など)が用いられることもある。
3. リハビリテーション
- 理学療法(PT): 筋力低下や関節拘縮の予防、歩行訓練、バランス訓練。
- 作業療法(OT): 感覚低下を補うための自助具の選定や使い方、日常生活動作(ADL)の工夫。
- 物理療法: 温熱療法による血流改善、TENS(経皮的電気神経刺激)による疼痛緩和。
看護のポイント
的確なアセスメント
- 症状の聴取(OPQRSTU)
- O (Onset): いつから?突然?徐々に?
- P (Provocation/Palliation): 何をすると悪化/軽快するか?(姿勢、時間帯、動作)
- Q (Quality): どんなしびれか?(ジンジン、ピリピリ、感覚がない)
- R (Region/Radiation): どこが?広がりは?(片側、両側、手袋靴下型、デルマトーム)
- S (Severity): どのくらい辛いか?(ペインスケールなど)
- T (Time course): 一日の中での変動は?
- U (Understanding): 患者自身が原因についてどう考えているか?
- 随伴症状の確認
筋力低下、痛み、呂律障害、頭痛、めまい、排尿障害などがないか。 - 既往歴・生活習慣の確認
糖尿病、甲状腺疾患、飲酒歴、使用中の薬剤など。
安全の確保と日常生活の援助
- 転倒・転落防止
感覚低下や筋力低下により、歩行やバランスが不安定になる。療養環境の整備(障害物の除去、手すりの設置)、適切な履物の選択、歩行器などの福祉用具の活用を検討する。 - 外傷・熱傷の予防
感覚が鈍くなっているため、怪我や火傷に気づきにくい。ストーブや湯たんぽの温度管理、足元の確認、入浴時の湯温の確認(温度計や家族による確認)を徹底する。フットケアを指導し、毎日足に傷がないか観察するよう促す。 - 日常生活動作(ADL)の援助
- 巧緻運動障害: ボタンのかけ外し、箸の使用、書字などが困難になることがある。マジックテープ式の衣類や、柄の太いスプーンなどの自助具を導入する。
- セルフケアの維持: 患者ができること・できないことを見極め、自立を促しつつ必要な部分を支援する。
苦痛の緩和
- 薬物療法の管理
鎮痛薬の効果と副作用(めまい、ふらつき、眠気など)を評価し、医師・薬剤師と連携する。副作用による転倒リスクにも注意する。 - 非薬物的アプローチ
- 安楽な体位の工夫: クッションなどを用いて、神経の圧迫を避け、安楽な体位を保つ。
- 温罨法・冷罨法: 血行を促進したり、炎症を抑えたりすることで症状が緩和することがある。患者の感覚や疾患に合わせて選択する。
- マッサージ: 循環を促し、リラクゼーション効果が期待できる。
- 気分転換: 趣味や会話など、患者が関心のあることに注意を向けることで、しびれや痛みへのとらわれを軽減する。
心理的・社会的支援
- 傾聴と共感
しびれは他者から見えにくく、辛さを理解されにくい症状である。「いつ治るのか」という不安や、日常生活の制限によるストレス、抑うつ状態に陥る患者も少なくない。患者の言葉に耳を傾け、その辛さを共感的に受け止める姿勢が、信頼関係の構築と治療意欲の向上につながる。 - 情報提供と意思決定支援
疾患や治療、今後の見通しについて、患者が理解できる言葉で説明し、不安を軽減する。患者が治療方針の決定に主体的に参加できるよう支援する。 - 社会資源の活用
必要に応じて、介護保険サービスの導入や身体障害者手帳の申請など、利用できる社会資源について情報提供し、ソーシャルワーカーなど多職種と連携する。