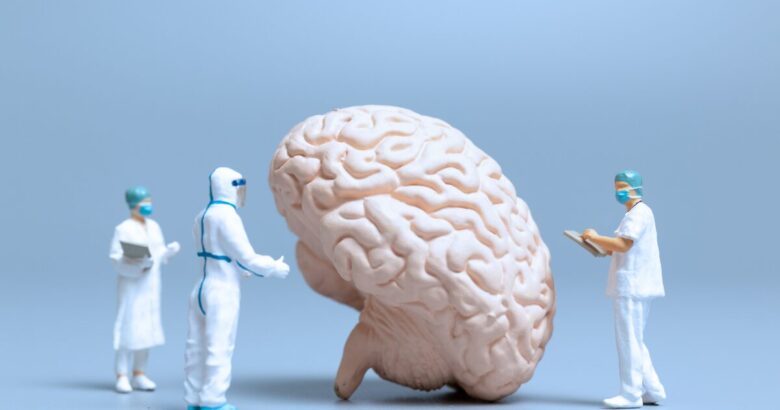その他の脳梗塞について徹底解説
 あずかん
あずかん脳梗塞は、アテローム血栓性脳梗塞、心原性脳塞栓症、ラクナ梗塞の3つの主要な病型に分類されることが一般的です。しかし、臨床現場ではこれらに分類できない、あるいは特殊な原因で発症する脳梗塞にも遭遇します。ここでは、「その他の脳梗塞」について、その病態生理、原因、症状、治療、そして看護のポイントを詳しく解説します。
その他の脳梗塞とは
アテローム血栓性、心原性、ラクナ梗塞に分類できない脳梗塞を総称して「その他の脳梗塞」と呼びます。原因は多岐にわたり、比較的まれな疾患も含まれますが、若年者の脳梗塞の原因となることも少なくありません。代表的なものとして、脳動脈解離、もやもや病、抗リン脂質抗体症候群などがあります。
代表的な疾患とそれぞれの特徴
脳動脈解離
病態生理
脳の血管壁は、内膜・中膜・外膜の3層構造になっています。脳動脈解離は、何らかの原因で内膜に亀裂が入り、そこから血液が流入して血管壁が裂けてしまう状態です。裂けた部分にできた偽腔(本来の血流路ではない空間)が膨らんで本来の血管(真腔)を狭窄・閉塞させたり、偽腔内にできた血栓が剥がれて末梢の血管を詰まらせたりすることで脳梗塞を発症します。
原因
- 外傷性: 交通事故やスポーツなどによる首への強い衝撃
- 非外傷性(特発性): 明確な原因はないが、遺伝的要因や結合組織の脆弱性が関与していると考えられています。カイロプラクティックやゴルフのスイング、咳やくしゃみなど、首を急にひねる動作が誘因となることもあります。
症状
- 特徴的な症状:
- 突然の激しい後頭部痛や頸部痛
- ホルネル症候群(眼瞼下垂、縮瞳、顔面の発汗低下)
- 脳梗塞による症状:
- めまい、ふらつき
- 構音障害
- 片麻痺、感覚障害
治療・対症療法
- 急性期治療:
- 抗血栓療法: 抗血小板薬や抗凝固薬(ヘパリン、ワルファリンなど)を用いて、血栓の形成を防ぎ、脳梗塞の再発を予防します。
- 血圧管理: 高血圧は解離を助長する可能性があるため、厳格な降圧管理が重要です。
- 血管内治療・外科的治療:
- 薬物療法で効果が不十分な場合や、解離が進行する場合に検討されます。ステント留置術やバイパス術などがあります。
看護のポイント
- 疼痛管理: 鎮痛薬の効果を評価し、患者さんが安楽に過ごせるよう援助します。
- 血圧コントロール: 頻回な血圧測定と、降圧薬の確実な投与、副作用の観察が重要です。
- 安静の保持: 頸部の回旋や伸展を避け、血圧の急激な変動を防ぐため、ベッド上安静の必要性を説明し、協力を得ます。
- 精神的ケア: 若年で発症することが多く、突然の発症に不安を抱える患者さんが少なくありません。傾聴や丁寧な説明を通じて、不安の軽減に努めます。
もやもや病
病態生理
内頸動脈の終末部(頭蓋内に入った先の部分)が原因不明に進行性に狭窄・閉塞し、その代償として脳底部に「もやもや血管」と呼ばれる異常な細い血管網が発達する疾患です。このもやもや血管は脆弱で破れやすく、脳出血の原因となる一方、脳の血流不足から脳梗塞も引き起こします。
原因
原因不明の疾患ですが、一部に家族内発症がみられることから、遺伝的素因の関与が考えられています。特に東アジアの若年層に好発します。
症状
- 小児と思春期:
- 一過性脳虚血発作(TIA): 啼泣(大泣き)や過呼吸(ハーモニカの演奏、熱い麺類を冷ますなど)をきっかけに、手足の脱力やしびれ、言語障害などが一時的に出現します。
- 成人:
- 脳出血: もやもや血管が破綻して発症します。突然の頭痛、意識障害、片麻痺など。
- 脳梗塞: 脳血流の低下により発症します。
治療・対症療法
- 外科的治療(血行再建術): 脳梗塞の発症や再発を予防するために、脳の血流を増やす手術が第一選択となります。
- 直接的血行再建術: 浅側頭動脈と中大脳動脈を吻合(STA-MCA吻合)します。
- 間接的血行再建術: 筋肉や硬膜などを脳表に置くことで、新生血管が発達するのを促します。
- 内科的治療: 抗血小板薬や抗てんかん薬が対症療法として用いられます。
看護のポイント
- 周術期管理: 血行再建術後の合併症(脳出血、脳梗塞、けいれんなど)の早期発見が重要です。バイタルサイン、意識レベル、神経学的所見を注意深く観察します。
- 過換気の回避: 過換気は脳血管を収縮させ、脳虚血を誘発するリスクがあります。特に小児例では、啼泣や過度の興奮を避けるような関わりが求められます。
- 生活指導: 退院後も過換気につながる行動(激しい運動、大泣きなど)を避ける必要性を、患者さん本人や家族に分かりやすく説明します。
- 成長・発達への配慮: 小児期に発症することが多いため、疾患や治療が患児の成長・発達、学校生活に与える影響をアセスメントし、多職種と連携して支援します。
抗リン脂質抗体症候群(APS)
病態生理
自身の体の成分であるリン脂質や、リン脂質に結合するタンパク質に対する自己抗体(抗リン脂質抗体)が産生される自己免疫疾患です。この抗体が血管内皮細胞などを攻撃し、血液が固まりやすい状態(過凝固状態)になるため、全身の動脈・静脈に血栓症を引き起こします。脳の動脈に血栓が形成されると脳梗塞を発症します。
原因
自己免疫の異常が原因ですが、詳細なメカニズムは不明です。全身性エリテマトーデス(SLE)などの膠原病に合併することがあります。
症状
- 血栓症: 脳梗塞、心筋梗塞、深部静脈血栓症、肺塞栓症など。
- 習慣性流産: 胎盤の血管に血栓ができることが原因とされています。
- その他: 血小板減少、皮膚症状(リベド)など。
治療・対症療法
- 抗血栓療法: 血栓症の治療と再発予防が治療の中心となります。
- 抗凝固療法: ワルファリンが第一選択薬です。プロトロンビン時間国際標準比(PT-INR)をモニタリングし、治療域を維持するようにコントロールします。
- 抗血小板療法: アスピリンなどが用いられることもあります。
- 基礎疾患の治療: SLEなどの膠原病が背景にある場合は、その治療も並行して行います。
看護のポイント
- 抗凝固療法の管理:
- ワルファリンの確実な内服管理と、食事(ビタミンKを多く含む食品の摂取)に関する指導が重要です。
- 定期的な採血(PT-INR)の必要性を説明します。
- 出血傾向(歯肉出血、鼻出血、皮下出血など)の有無を観察し、早期発見に努めます。
- 全身の血栓症の観察: 脳梗塞以外の血栓症(下肢の腫脹・疼痛、突然の呼吸困難・胸痛など)の兆候にも注意を払います。
- 精神的ケアと療養生活支援:
- 生涯にわたる治療が必要となることが多く、患者さんは疾患を抱えながら生活することへの不安を抱きがちです。疾患を正しく理解し、治療を継続できるよう支援します。
- 妊娠・出産を希望する女性患者さんには、専門医と連携し、適切な情報提供と精神的サポートを行います。