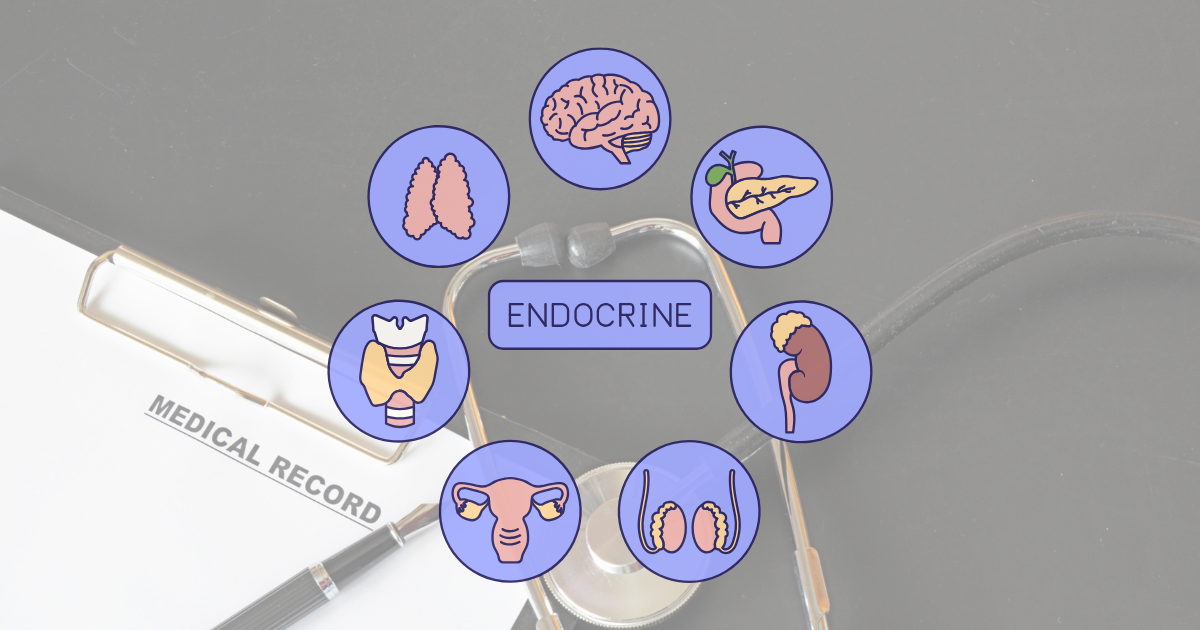糖尿病網膜症の病態から看護のポイントまで徹底解説
 あずかん
あずかん糖尿病の三大合併症の一つである「糖尿病網膜症」。失明の原因にもなりうるこの疾患は、患者さんのQOLに大きく影響します。
この記事では、糖尿病網膜症の基本的な知識から、具体的な看護のポイントまでを分かりやすく解説します。
糖尿病網膜症とは
糖尿病網膜症は、高血糖状態が長期間続くことによって、眼の奥にある「網膜」の血管が障害されることで発症します。そもそも網膜は、カメラでいうフィルムの役割を果たす非常に重要な組織で、光を感じ取り、その情報を脳に送っています。
しかし高血糖により、網膜の毛細血管は少しずつダメージを受け、変形したり詰まったりします。この状態が「単純糖尿病網膜症」です。
血管が詰まると、網膜に十分な酸素や栄養が届かなくなり、虚血状態に陥ります。すると、体は新しい血管(新生血管)を作って酸素不足を補おうとします。しかし、この新生血管は非常にもろく、破れやすいのが特徴です。この段階が「増殖前糖尿病網膜症」です。
さらに進行すると、破れやすい新生血管が硝子体に向かって伸びていきます。これが「増殖糖尿病網膜症」です。新生血管が破れると、硝子体出血を引き起こし、急激な視力低下を招きます。また、出血が吸収される過程で増殖膜という線維組織が形成され、これが網膜を引っ張ることで「牽引性網膜剥離」を引き起こすこともあります。
さらに、黄斑部(網膜の中心で、最も視力に関わる部分)に血液中の成分が漏れ出して浮腫を起こす「糖尿病黄斑浮腫」も、どの病期でも起こりうる合併症であり、視力低下の大きな原因となります。
糖尿病網膜症の原因
糖尿病網膜症の直接的な原因は、長期間にわたる高血糖です。血糖値が高い状態が続くことで、血管の内皮細胞が障害され、血管壁の透過性が亢進したり、血流が悪化したりします。
特に、以下の因子は発症リスクを高めると言われています。
高血糖の罹病期間: 糖尿病を発症してからの期間が長くなるほど、網膜症の発症率は高まります。
血糖コントロール不良: HbA1cが高い状態が続くと、網膜症は進行しやすくなります。
高血圧: 高血圧は血管に負担をかけるため、網膜症を悪化させる大きな要因です。
脂質異常症: 血中の脂質が多いと、血管が詰まりやすくなり、網膜症のリスクを高めます。
妊娠: 妊娠中は血糖コントロールが不安定になりやすく、網膜症が急速に進行することがあります。
腎症: 糖尿病腎症を合併している場合、網膜症も進行していることが多いとされています。
糖尿病網膜症の症状
糖尿病網膜症は「サイレントキラー」とも呼ばれ、初期段階では自覚症状がほとんどありません。
- 初期(単純・増殖前網膜症)
- ほとんど症状はありません。かすみ目などを感じることがあっても、一過性の場合が多く、見過ごされがちです。
- 進行期(増殖網膜症)
- 飛蚊症: 硝子体出血により、目の前に蚊やゴミのようなものが飛んでいるように見えます。
- 急激な視力低下: 大量の硝子体出血や、網膜剥離によって引き起こされます。
- 視野欠損: 網膜剥離が起こると、カーテンがかかったように視野の一部が見えなくなります。
- 糖尿病黄斑浮腫
- 視力低下: ものがぼやけて見えたり、かすんで見えたりします。
- 変視症: まっすぐな線が歪んで見えます。
自覚症状が出たときには、すでに病状がかなり進行しているケースが多いため、症状の有無にかかわらず定期的な眼科受診が不可欠です。
治療・対症療法
治療の主な目的は、網膜症の進行を抑制し、現在の視力を維持することです。一度失われた視力を完全に取り戻すことは困難な場合が多いため、早期発見・早期治療が重要となります。
血糖コントロール
全ての治療の基本です。良好な血糖コントロールを維持することが、網膜症の発症予防と進行抑制に最も効果的です。
薬物療法
- 抗VEGF薬硝子体内注射
- 糖尿病黄斑浮腫や新生血管の発生を抑制するために、VEGF(血管内皮増殖因子)の働きを抑える薬剤を直接眼内に注射します。現在、治療の第一選択となっています。
- ステロイド薬硝子体内注射
- 黄斑浮腫を抑えるためにステロイド薬を眼内に注射することもあります。
レーザー治療
- 網膜光凝固術
- 虚血状態の網膜にレーザーを照射し、新生血管の発生を防ぎ、すでにある新生血管を焼き固める治療法です。網膜症の進行を抑制する目的で行われます。
手術療法
- 硝子体手術
- 硝子体出血や牽引性網膜剥離が起きた場合に、出血や増殖膜を取り除く手術です。
血圧・脂質管理
高血圧や脂質異常症の管理も、網膜症の進行を抑える上で非常に重要です。食事療法、運動療法、薬物療法を組み合わせて行います。
看護のポイント
心理的サポートと教育
- 疾患の正しい理解を促す
- 「症状がないから大丈夫」という思い込みが治療中断につながるため、初期段階では自覚症状がないことを繰り返し説明します。視力低下の不安や恐怖を傾聴し、精神的なサポートを行います。
- 治療の必要性を説明する
- 各治療法(特に注射やレーザー)の目的、効果、副作用について分かりやすく説明し、患者が安心して治療を受けられるように支援します。
セルフケア行動の支援
- 血糖コントロールの重要性を強調
- 日々の血糖測定や食事療法、運動療法が、目の健康を守るためにいかに重要であるかを、病態と関連付けて説明します。
- 定期的な眼科受診の徹底
- 症状がなくても、指定された間隔で必ず眼科を受診する必要があることを強調します。「見え方が変わらなくても、眼の中では変化が起きている可能性がある」ことを伝えます。
- 日常生活での注意点を指導
- 視力低下がある場合: 転倒予防のための環境整備(部屋を明るくする、障害物を置かないなど)を家族にも協力してもらいながら行います。
- 薬物療法(点眼薬など): 正しい点眼手技を指導し、患者自身で行うのが難しい場合は家族の協力や補助具の活用を検討します。
- 手術後のケア: 安静度や体位制限、保護眼帯の装着など、医師の指示に基づいたケアが守られるよう支援します。
多職種との連携
眼科医、内科医、管理栄養士、薬剤師など、多職種と密に連携し、患者の情報を共有することが重要です。特に、内科での血糖コントロール状況と、眼科での網膜症の進行度を常に把握し、一貫したケアを提供できるよう調整役を担います。