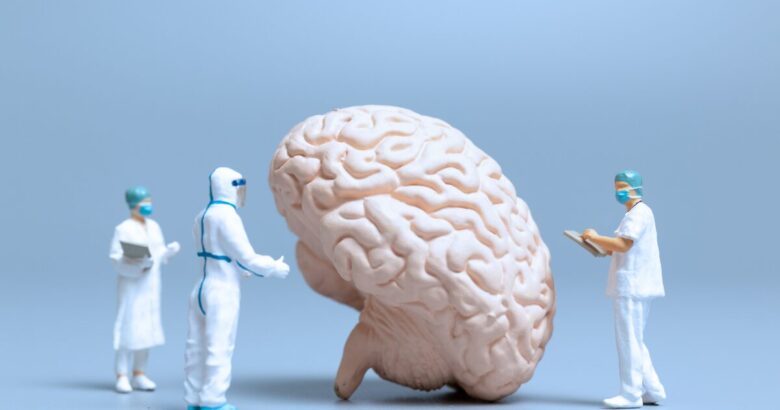心原性脳塞栓症の病態から看護のポイントまで徹底解説
 あずかん
あずかん脳梗塞の中でも、特に重症化しやすく、突然発症することが多い「心原性脳塞栓症」。心臓にできた血栓が脳の血管に詰まることで起こるこの疾患は、迅速な対応と専門的な看護が求められます。
この記事では、心原性脳塞栓症の基本的な知識から、臨床現場で役立つ看護のポイントまでを分かりやすく解説します。
心原性脳塞栓症とは
心原性脳塞栓症は、その名の通り「心臓」が「原因」となって脳の血管が詰まる(塞栓)ことで発症します。
主なメカニズムは以下の通りです。
1.心臓内での血栓形成
心房細動などの不整脈や心臓弁膜症などにより、心臓内の血液の流れがよどみ、「血栓」が形成されます。特に、心房細動では心房の収縮が不規則になるため、左心耳と呼ばれる部分に血栓ができやすくなります。
2.血栓の移動
心臓内にできた血栓が、拍動によって血流に乗り、大動脈を通って脳へと運ばれます。
3.脳血管の閉塞
脳に到達した血栓は、脳の太い血管(中大脳動脈など)に詰まり、その先の脳組織への血流を完全に遮断してしまいます。
4.脳組織の壊死
血流が途絶えた脳組織は、酸素や栄養が供給されなくなり、短時間で不可逆的なダメージを受け、壊死に至ります。
アテローム血栓性脳梗塞が徐々に血管が狭くなるのに対し、心原性脳塞栓症では比較的大きな血栓が突然血管を詰まらせるため、広範囲の脳梗塞を引き起こし、重篤な症状が出やすいのが特徴です。
心原性脳塞栓症の主な原因
心原性脳塞栓症の最大の原因は「非弁膜症性心房細動」であり、全体の約7割を占めると言われています。
心房細動
心房が不規則に細かく震える不整脈です。心房が正常に収縮しないため、心臓内の血流が滞り、血栓ができやすくなります。加齢とともに有病率が上昇します。
弁膜症
心臓の弁に異常が生じる疾患で、特に僧帽弁狭窄症などで血栓のリスクが高まります。
心筋梗塞
心筋梗塞によって心臓の壁の動きが悪くなると、その部分に血栓(壁在血栓)が形成されることがあります。
感染性心内膜炎
心臓の弁や心内膜に細菌が付着し、「疣贅」と呼ばれるできものが形成されます。この疣贅の一部が剥がれて脳に飛ぶことで塞栓症を引き起こします。
脳梗塞による症状
血栓が突然、太い血管を塞ぐため、症状は突発的に完成型で現れることが特徴です。意識障害を伴うことも少なくありません。
代表的な症状(FAST)を覚えておきましょう。
Face(顔): 顔の片側が下がる、ゆがむ。
Arm(腕): 片方の腕に力が入らない、上がらない。
Speech(言葉): ろれつが回らない、言葉が出ない、他人の言うことが理解できない。
Time(時間): 発症時刻の確認が重要。すぐに救急車を呼びましょう。
その他、以下のような症状が見られます。
- 片麻痺: 体の片側の手足が動かなくなる。
- 感覚障害: 体の片側の感覚が鈍くなる、しびれる。
- 失語症: 言葉を話す、理解することが困難になる。
- 同名半盲: 視野の左右どちらか半分が見えなくなる。
- 意識障害: 呼びかけに反応が鈍い、意識がなくなる。
治療と対症療法
治療の目標は、閉塞した血管の再開通と、脳組織の保護、そして再発予防です。
急性期治療
- 血栓溶解療法(t-PA静注療法)
- 発症4.5時間以内が適応となる治療法。t-PA(組織プラスミノーゲンアクチベータ)という薬剤を点滴し、血栓を強力に溶かします。
- 機械的血栓回収療法
- カテーテルを脳の血管まで進め、ステント型リトリーバーや吸引カテーテルを用いて、物理的に血栓を回収します。発症から24時間以内(条件による)まで適応が拡大しており、t-PAで効果がなかった場合や適応外の場合にも行われます。
再発予防
- 抗凝固療法
- 再発予防の要となる治療です。心臓内に新たな血栓ができるのを防ぐために、抗凝固薬(DOAC:直接経口抗凝固薬、ワルファリンなど)を内服します。
- ワルファリン: 古くから使われている薬。納豆やクロレラなど、ビタミンKを多く含む食品の摂取制限が必要です。定期的な採血で効果(PT-INR)を確認し、投与量を調整する必要があります。
- DOAC: 食事制限がなく、出血性合併症のリスクがワルファリンより低いとされています。複数の種類があり、患者さんの状態に合わせて選択されます。
- 再発予防の要となる治療です。心臓内に新たな血栓ができるのを防ぐために、抗凝固薬(DOAC:直接経口抗凝固薬、ワルファリンなど)を内服します。
対症療法
- 脳保護療法
- 脳浮腫を軽減するために、グリセオールなどを投与します。
- リハビリテーション
- 急性期から早期に開始し、機能回復を目指します。理学療法(PT)、作業療法(OT)、言語聴覚療法(ST)があります。
看護のポイント
急性期の看護
- バイタルサインの厳重な管理
- 特に血圧の管理が重要です。血圧が高すぎると出血性梗塞のリスクが高まり、低すぎると脳血流が低下するため、医師の指示に基づいた目標範囲内にコントロールします。
- 神経症状の観察
- 意識レベル(JCS, GCS)、瞳孔所見、麻痺の程度などを経時的に評価し、変化の早期発見に努めます。「昨日と比べてどうか」という視点が大切です。
- t-PA・血栓回収療法後の管理
- 出血リスクの観察: 穿刺部の止血確認、口腔内や尿中の出血の有無、頭痛や嘔気などの頭蓋内出血の徴候に注意します。
- 再開通の評価: 治療後に麻痺が改善するなど、症状の変化を注意深く観察します。
- 誤嚥性肺炎の予防
- 嚥下障害を合併することが多いため、口腔ケアを徹底し、初回経口摂取前には必ず嚥下評価(反復唾液嚥下テストなど)を行います。
- 安全管理
- 意識障害や麻痺により、転倒・転落のリスクが非常に高い状態です。ベッドサイドの環境整備や、必要に応じたセンサーマットの活用など、安全確保に努めます。
回復期・慢性期の看護
- 抗凝固療法の服薬管理と指導
- 確実な服薬: 退院後も継続的な内服が再発予防に不可欠であることを伝え、アドヒアランスを高めるための支援を行います。
- 出血傾向への注意: 歯磨き時の歯肉出血、鼻血、皮下出血、血尿・血便などの症状に注意し、異常があればすぐに相談するよう指導します。
- ワルファリンの場合: 食事制限(納豆、クロレラ、青汁など)の重要性を繰り返し説明します。
- 再発予防のための生活指導
- 原因疾患の管理: 心房細動などの原因疾患の治療を継続することの重要性を説明します。
- 生活習慣の改善: 高血圧、糖尿病、脂質異常症など、他の危険因子も管理できるよう、食事や運動について指導します。
- 精神的・社会的サポート
- 突然の発症と後遺症により、患者や家族は大きな不安を抱えています。思いや訴えを傾聴し、精神的なサポートを行うとともに、必要に応じて医療ソーシャルワーカー(MSW)と連携し、退院後の生活や社会資源の活用について支援します。